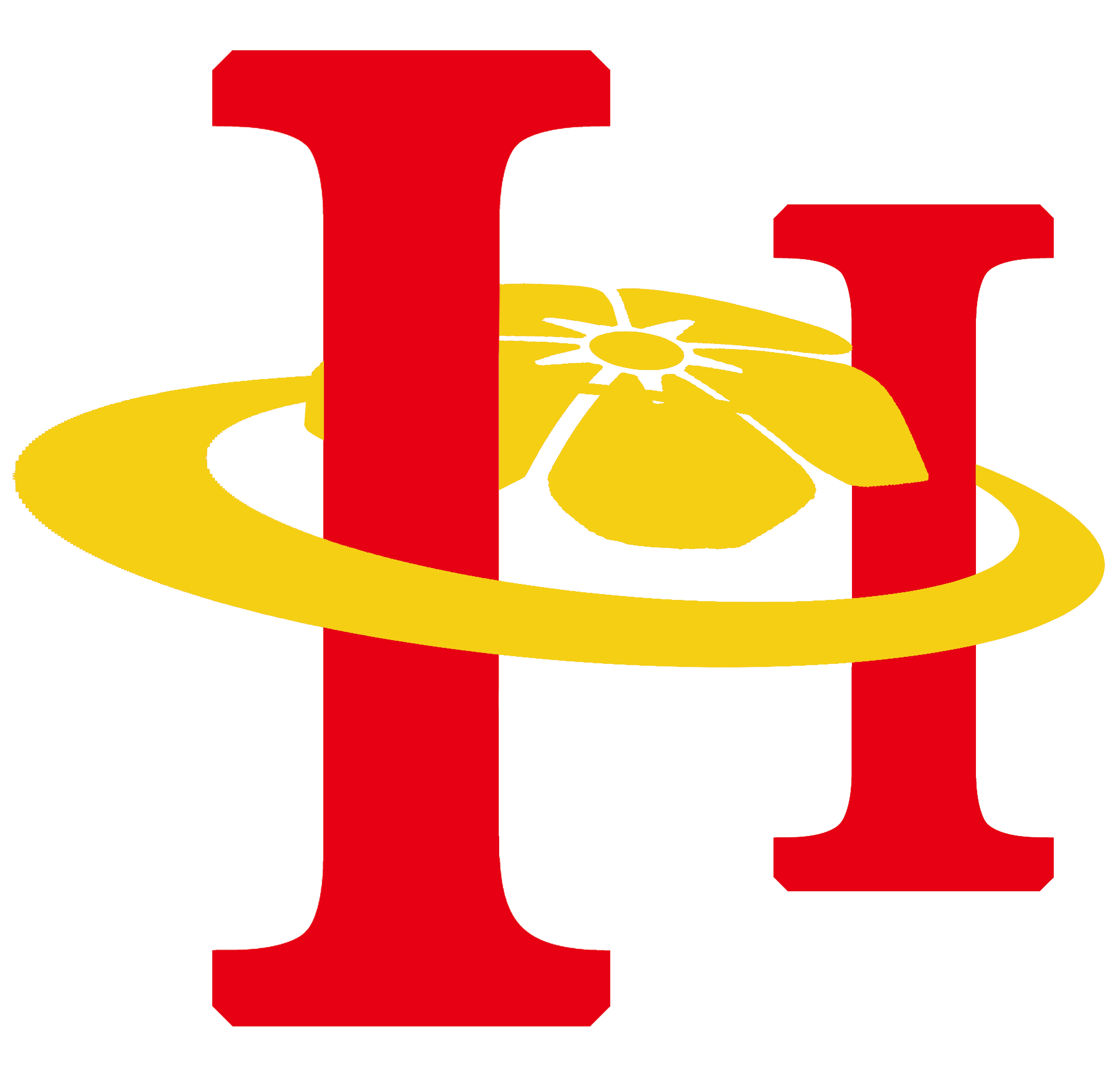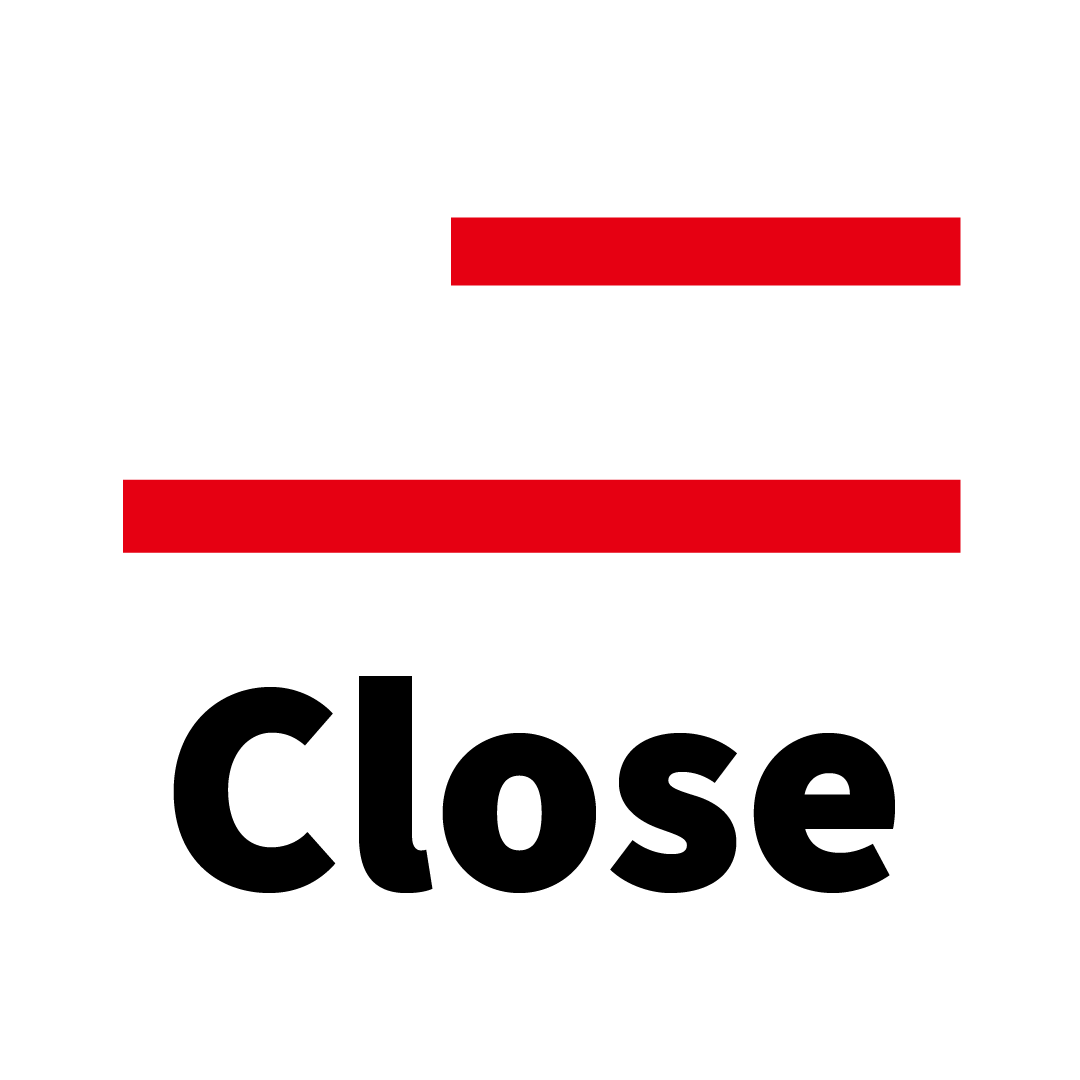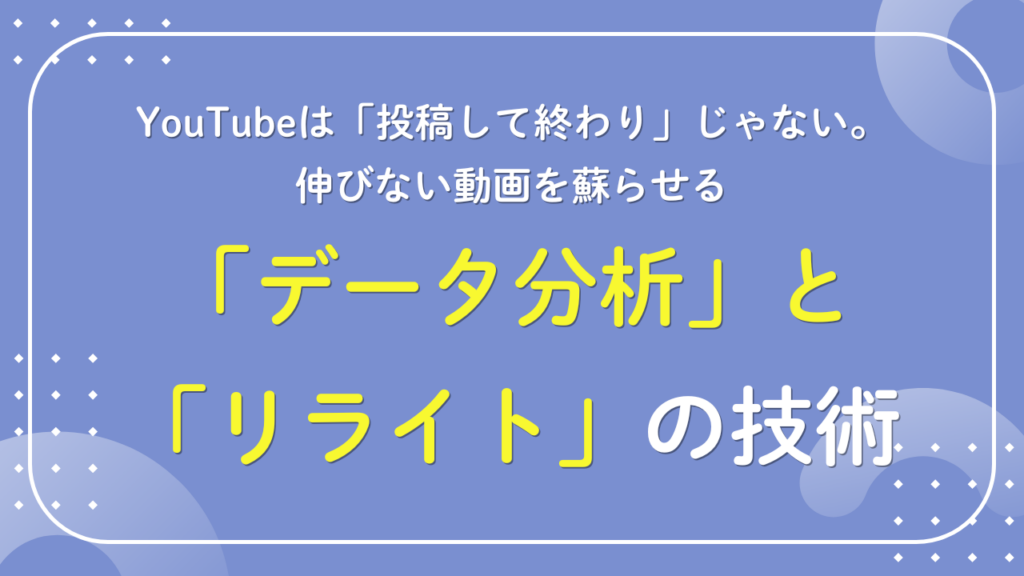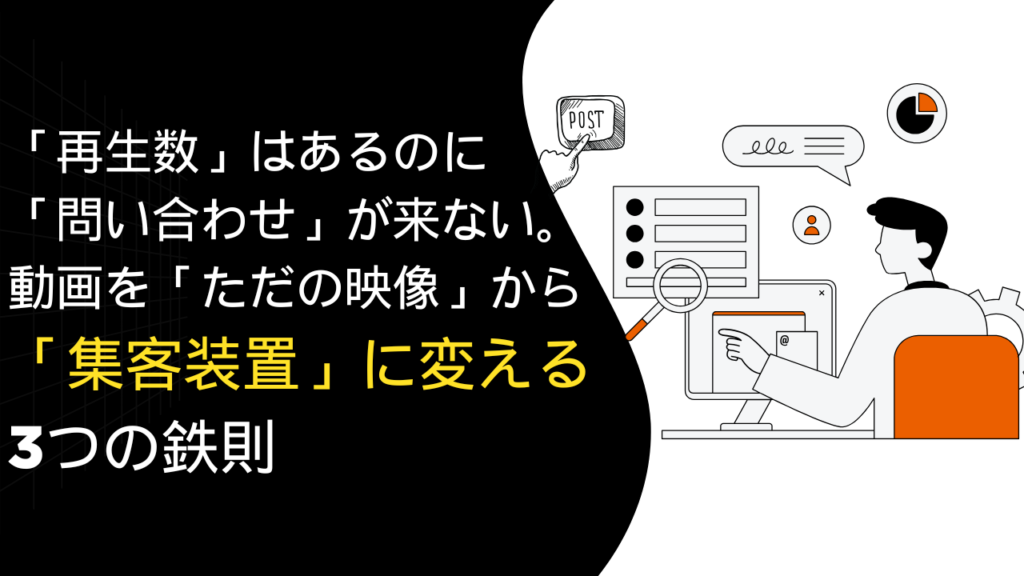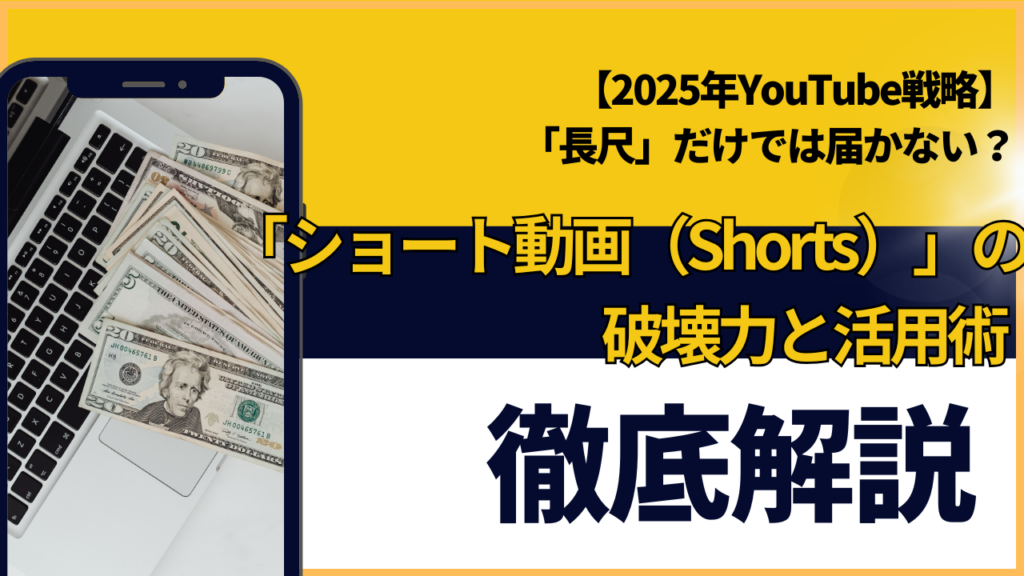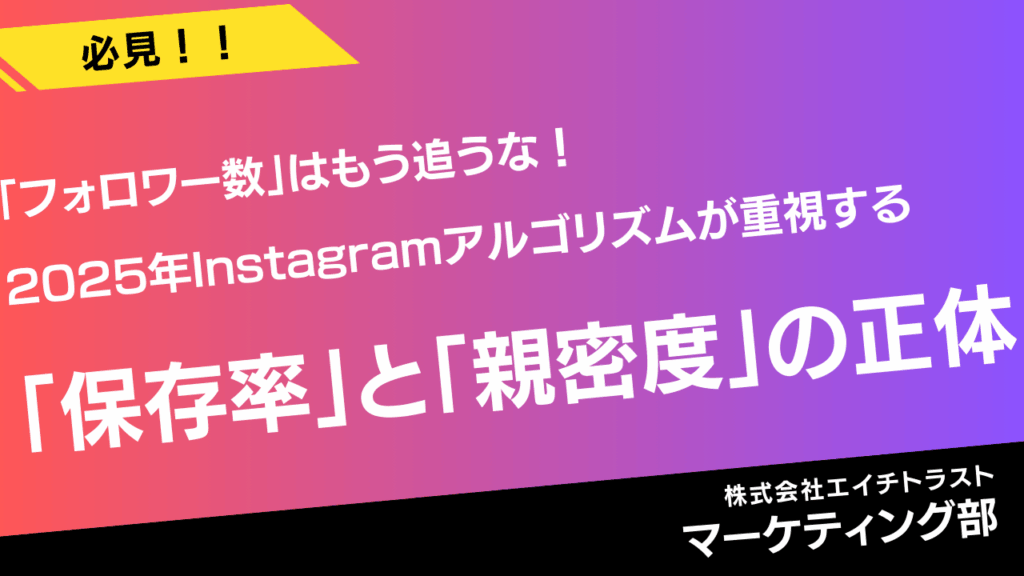AWSと業務知識—技術とビジネスの“橋渡し”を意識するようになった話-エンジニアA-

こんにちは、エンジニアAです。
現在システムエンジニアとして、主にクラウドを活用したシステム開発・運用に携わっています。中でも最近、特に強く感じているのが、「AWSなどのクラウド技術」と「業務知識」の両方をバランスよく理解しておくことの重要性です。
クラウドの世界では、数年前に比べて圧倒的に選択肢が増え、サービスもどんどん細分化されています。AWSで言えば、EC2、S3、RDS、Lambda、CloudWatch、IAM、CloudFormation…といった代表的なサービスに加えて、機械学習やデータ分析の領域まで含めると、もはや“全部を知る”のは現実的ではありません。
その中で私自身が意識しているのは、「技術に詳しくなること」以上に「どの技術が、どの業務課題に対して意味を持つのか」を常に考えることです。たとえば、あるクライアントが「サーバ管理の手間を減らしたい」と話したとき、それが単なるEC2インスタンスの自動化で済む話なのか、もしくは思い切ってFargateやLambdaを採用した方がいいのか、業務の実態を知らないと適切な判断はできません。
業務知識というのは、単に業種ごとの“単語”を知っているだけでは意味がありません。どんなフローで業務が回っていて、どこにボトルネックや無駄があるのか、業務上の制約(法規制、承認フロー、リードタイムなど)をどうシステムで吸収するのか。こうした「業務全体の構造」を理解して初めて、AWSの持つ“柔軟さ”や“スケーラビリティ”を正しく活かすことができるのだと思います。
最近担当したあるプロジェクトでは、営業部門の受発注業務をWeb化する案件において、業務の流れに応じてデータベース設計を見直し、それに合わせてAurora Serverlessを採用しました。ピーク時と閑散時のリソース差が大きいことが予測されたため、従来のRDSよりもコスト面で効率化が図れる判断です。これは単に「Aurora Serverlessのほうが新しいから」ではなく、「その業務に合っていたから」採用できたものです。
また、AWSに限らず、クラウドインフラは「安く・速く・柔軟に」を体現できる強力なツールですが、それを最大限に活かすには、クライアントが抱えているビジネス的な悩みや制約条件を深く理解する必要があります。たとえば、ある業務では「毎月月末だけアクセスが急増する」「外部との連携は全てCSVファイルでやり取りされる」「クラウドは使いたいが、データは国内に置いておきたい」など、非技術的な要件が多く存在します。
こうした“文脈”を理解しないままAWSの提案をすると、「それはうちには合わない」と言われてしまいますし、逆に業務の裏側まで理解した上で提案すると、「ちゃんと分かってくれている」という信頼感につながります。
結局、クラウドを使いこなすというのは、AWSのドキュメントを読破することではなく、「お客様の業務や課題をクラウドという道具でどう支えるか」を考え続けることだと感じます。そして、業務知識は一朝一夕では身につかないので、ヒアリングや現場観察、関係者との会話などを通じて少しずつ積み重ねていくしかありません。
技術力と業務理解。どちらか一方に偏るのではなく、その“橋渡し”ができる存在こそが、これからのシステムエンジニアに求められる役割だと思っています。まだまだ自分自身も発展途上ですが、これからも「技術だけでは解けない課題」に向き合いながら、AWSの知識と業務知識の両輪で価値を出していけるよう努力していきたいと思います。

こんにちは、エンジニアAです。
現在システムエンジニアとして、主にクラウドを活用したシステム開発・運用に携わっています。中でも最近、特に強く感じているのが、「AWSなどのクラウド技術」と「業務知識」の両方をバランスよく理解しておくことの重要性です。
クラウドの世界では、数年前に比べて圧倒的に選択肢が増え、サービスもどんどん細分化されています。AWSで言えば、EC2、S3、RDS、Lambda、CloudWatch、IAM、CloudFormation…といった代表的なサービスに加えて、機械学習やデータ分析の領域まで含めると、もはや“全部を知る”のは現実的ではありません。
その中で私自身が意識しているのは、「技術に詳しくなること」以上に「どの技術が、どの業務課題に対して意味を持つのか」を常に考えることです。たとえば、あるクライアントが「サーバ管理の手間を減らしたい」と話したとき、それが単なるEC2インスタンスの自動化で済む話なのか、もしくは思い切ってFargateやLambdaを採用した方がいいのか、業務の実態を知らないと適切な判断はできません。
業務知識というのは、単に業種ごとの“単語”を知っているだけでは意味がありません。どんなフローで業務が回っていて、どこにボトルネックや無駄があるのか、業務上の制約(法規制、承認フロー、リードタイムなど)をどうシステムで吸収するのか。こうした「業務全体の構造」を理解して初めて、AWSの持つ“柔軟さ”や“スケーラビリティ”を正しく活かすことができるのだと思います。
最近担当したあるプロジェクトでは、営業部門の受発注業務をWeb化する案件において、業務の流れに応じてデータベース設計を見直し、それに合わせてAurora Serverlessを採用しました。ピーク時と閑散時のリソース差が大きいことが予測されたため、従来のRDSよりもコスト面で効率化が図れる判断です。これは単に「Aurora Serverlessのほうが新しいから」ではなく、「その業務に合っていたから」採用できたものです。
また、AWSに限らず、クラウドインフラは「安く・速く・柔軟に」を体現できる強力なツールですが、それを最大限に活かすには、クライアントが抱えているビジネス的な悩みや制約条件を深く理解する必要があります。たとえば、ある業務では「毎月月末だけアクセスが急増する」「外部との連携は全てCSVファイルでやり取りされる」「クラウドは使いたいが、データは国内に置いておきたい」など、非技術的な要件が多く存在します。
こうした“文脈”を理解しないままAWSの提案をすると、「それはうちには合わない」と言われてしまいますし、逆に業務の裏側まで理解した上で提案すると、「ちゃんと分かってくれている」という信頼感につながります。
結局、クラウドを使いこなすというのは、AWSのドキュメントを読破することではなく、「お客様の業務や課題をクラウドという道具でどう支えるか」を考え続けることだと感じます。そして、業務知識は一朝一夕では身につかないので、ヒアリングや現場観察、関係者との会話などを通じて少しずつ積み重ねていくしかありません。
技術力と業務理解。どちらか一方に偏るのではなく、その“橋渡し”ができる存在こそが、これからのシステムエンジニアに求められる役割だと思っています。まだまだ自分自身も発展途上ですが、これからも「技術だけでは解けない課題」に向き合いながら、AWSの知識と業務知識の両輪で価値を出していけるよう努力していきたいと思います。