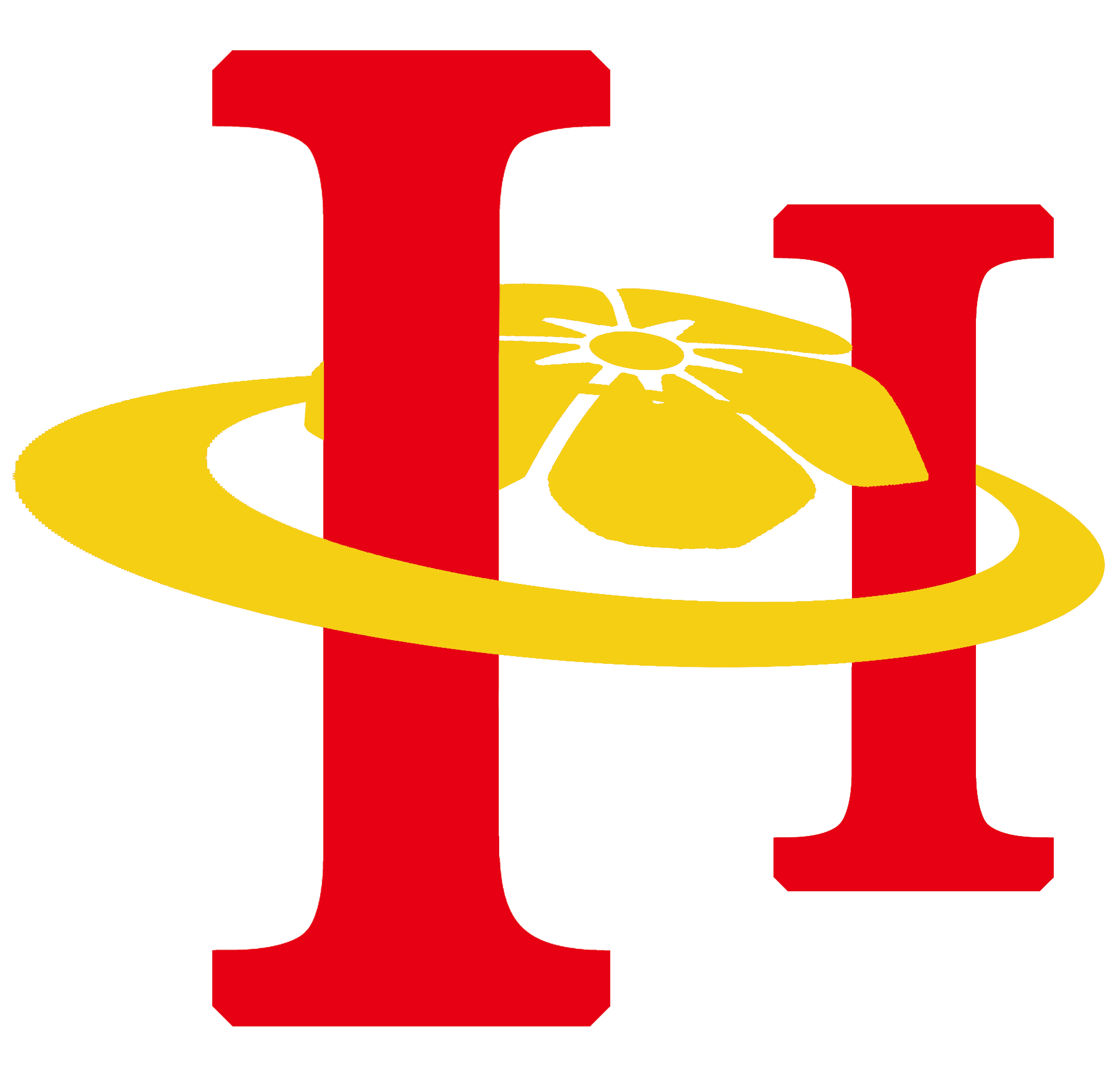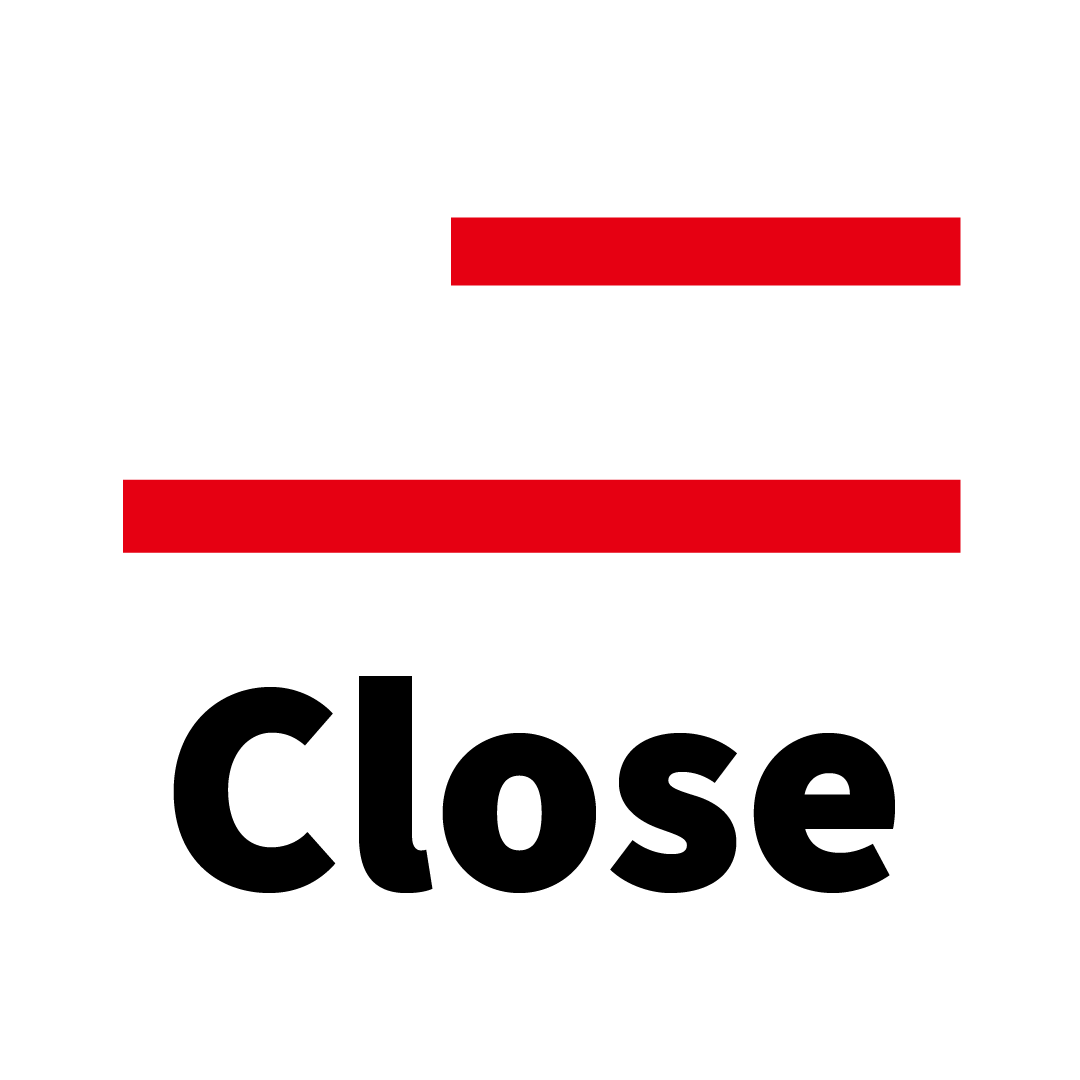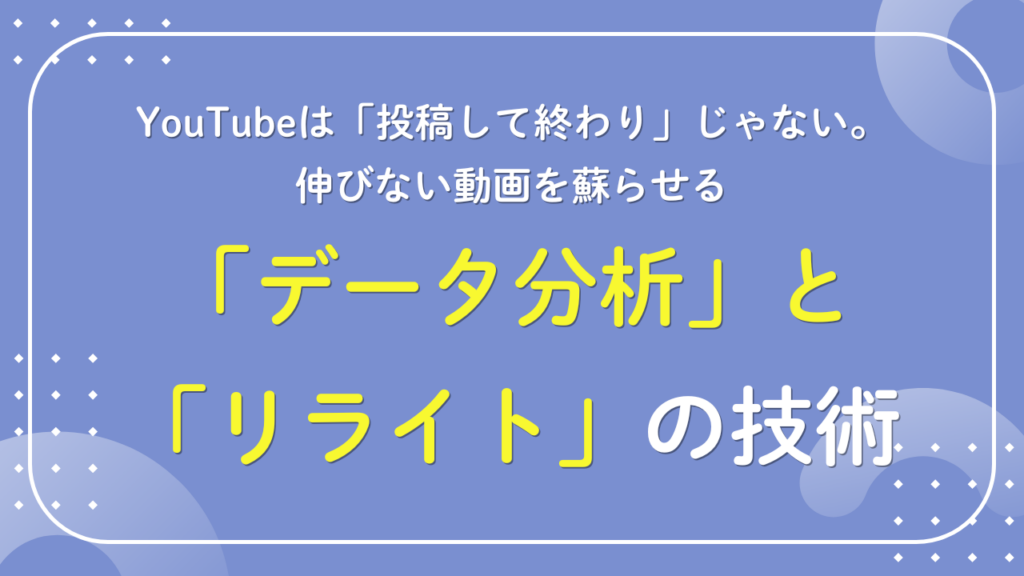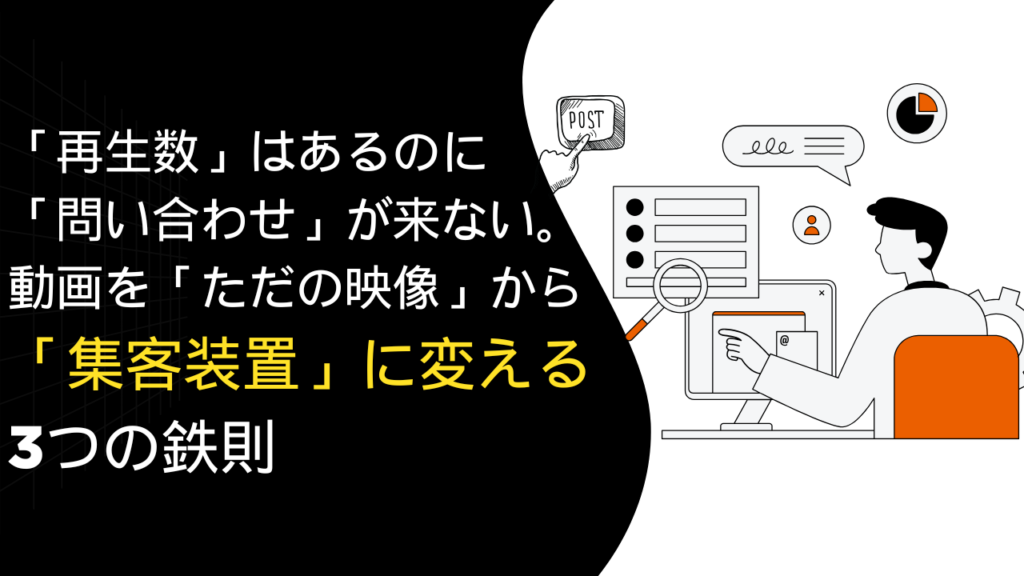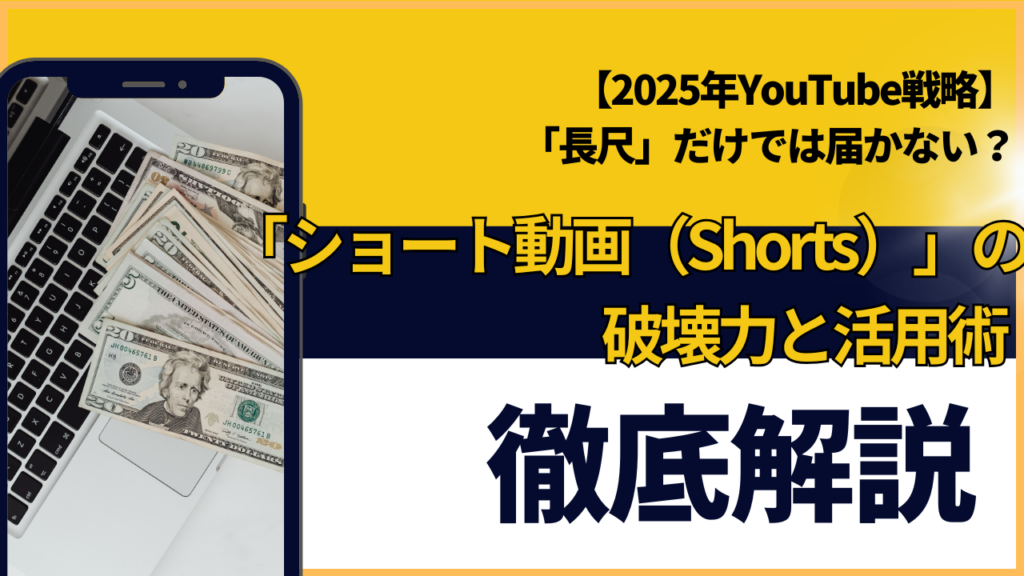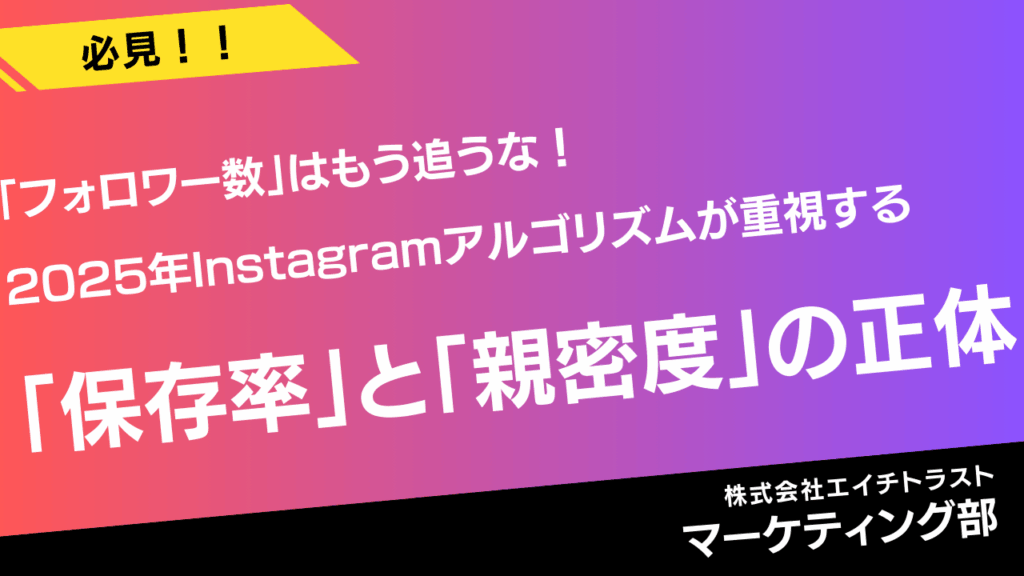開発者がFigmaを使いこなすべき理由-エンジニアA-
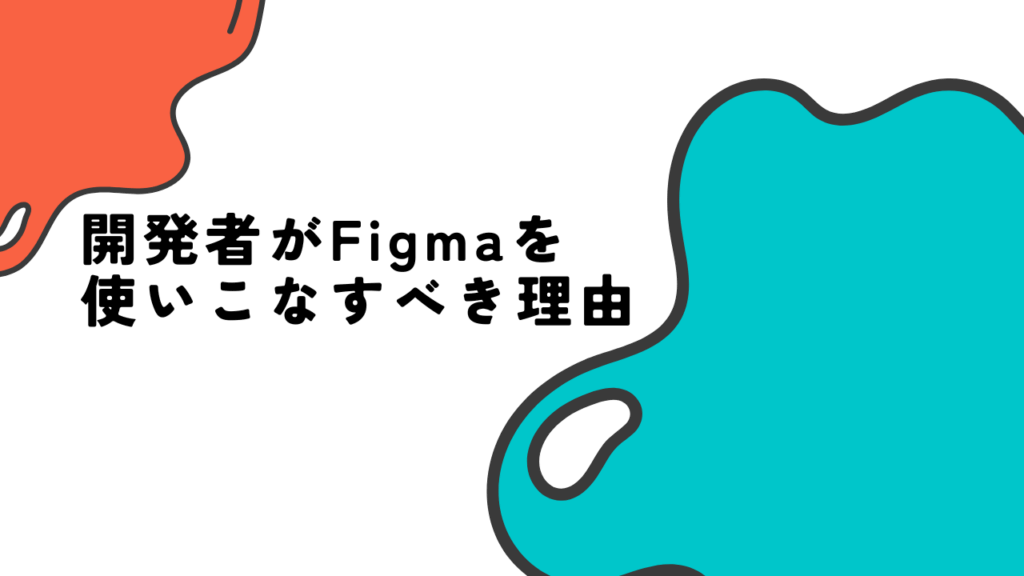
Web開発において、「デザインはデザイナーの仕事」と線引きする時代は終わりを迎えつつあります。フロントエンドエンジニア、特にUIを扱う立場であればあるほど、Figmaのようなデザインツールを理解し、活用できることは大きな武器になります。今回は、なぜ開発者がFigmaを“使いこなす”べきなのか、その理由を掘り下げてみたいと思います。
1. デザインの意図を正しく読み取れるようになる
Figmaを触り慣れていないエンジニアは、渡されたデザインを「静的な見た目の指示」としてしか受け取らないことがあります。しかし、Figmaの中には余白、フォント階層、レスポンシブな想定、コンポーネントの再利用性など、設計の意図が詰まっています。
Figmaを使いこなすことで、「このボタンのマージンは全体のバランスを取るために設計されている」「このカラーはブランドカラーと補色で構成されている」といった文脈や意図を読み解く力が身につきます。これにより、実装の精度も格段に上がります。
2. デザイナーとの共通言語を持てる
「このパーツ、オートレイアウトで作ってるから構造崩れないですよ」と言われて理解できなかった経験はないでしょうか?Figmaは、UI設計における構造的な概念(オートレイアウト、コンポーネント、バリアントなど)を備えており、開発とデザインの橋渡し役として機能します。
エンジニアがFigmaを扱えることで、デザイナーとのやりとりも非常にスムーズになります。伝達コストが減ることで、「デザインデータの解釈違い」「差し戻しによる手戻り」など、開発現場でありがちな問題を減らせます。
3. 修正依頼を自分で処理できるようになる
ちょっとした修正、例えば「このテキストを太字にする」「アイコンを10px右にずらす」などは、いちいちデザイナーに依頼するよりも、Figmaを開いて自分で変更確認できた方が早いです。
もちろん本番のデザインを勝手に書き換えることは推奨されませんが、クローンを作って挙動をシミュレートしたり、修正内容を明示的に共有したりできるようになると、スピード感のある開発が実現します。
4. デザインからCSSや値を正確に読み取れる
Figmaは、CSS情報(フォントサイズ、カラーコード、ボックスシャドウなど)をインスペクトモードで確認できます。これにより、スタイルの再現性が非常に高くなります。
特に、色やフォントの一貫性を担保したいときや、複雑なマージン設計の解析が必要なときに、Figmaを理解していることは大きなアドバンテージになります。
5. UI品質への感度が上がる
Figmaを日常的に使うことで、「あれ、このボタンのサイズ、他とズレてるな」といった微細なズレや違和感に気付く力が養われます。これは単なる視覚の訓練というより、“UI全体の設計思想を読む”力です。
この感度が育つと、設計の一貫性を保ちながら、ユーザー体験を損なわない改善提案ができるようになります。
Figmaは“開発のツール”でもある
Figmaは単なるデザインツールではなく、開発とデザインの接続点であり、エンジニアにとっても重要な「プロジェクト理解ツール」だと私は思っています。
「デザイナーが作ったものを再現する」という受け身の姿勢から、「UIの品質をともに作り上げる」立場へと、エンジニアのあり方は進化しています。Figmaを使いこなすことは、その第一歩なのではないでしょうか。
もし、まだFigmaに抵抗感がある方がいれば、まずは自分のプロジェクトのデザインデータを“触ってみる”ことから始めてみてください。意外とシンプルで、楽しい世界が広がっているかもしれません。
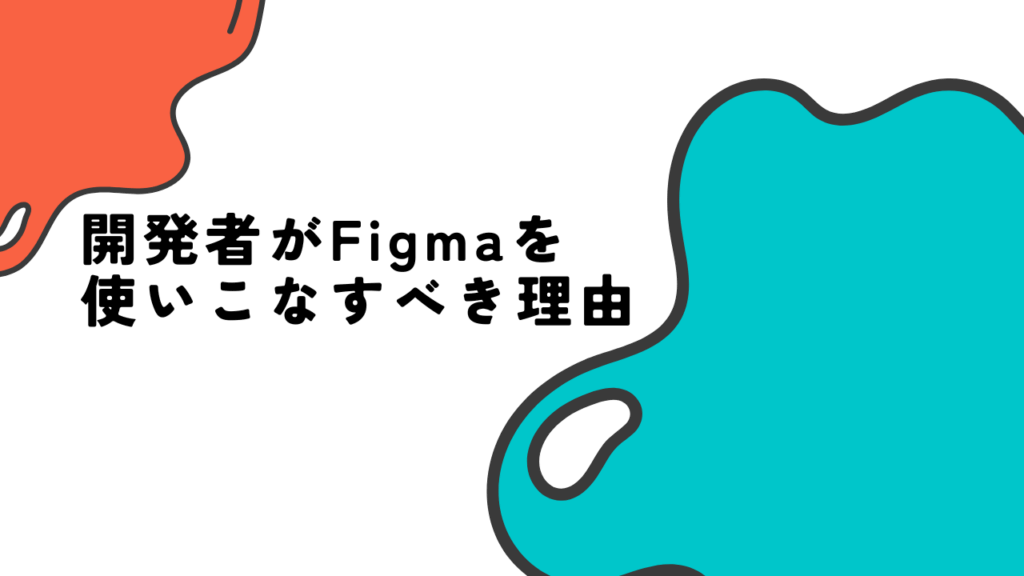
Web開発において、「デザインはデザイナーの仕事」と線引きする時代は終わりを迎えつつあります。フロントエンドエンジニア、特にUIを扱う立場であればあるほど、Figmaのようなデザインツールを理解し、活用できることは大きな武器になります。今回は、なぜ開発者がFigmaを“使いこなす”べきなのか、その理由を掘り下げてみたいと思います。
1. デザインの意図を正しく読み取れるようになる
Figmaを触り慣れていないエンジニアは、渡されたデザインを「静的な見た目の指示」としてしか受け取らないことがあります。しかし、Figmaの中には余白、フォント階層、レスポンシブな想定、コンポーネントの再利用性など、設計の意図が詰まっています。
Figmaを使いこなすことで、「このボタンのマージンは全体のバランスを取るために設計されている」「このカラーはブランドカラーと補色で構成されている」といった文脈や意図を読み解く力が身につきます。これにより、実装の精度も格段に上がります。
2. デザイナーとの共通言語を持てる
「このパーツ、オートレイアウトで作ってるから構造崩れないですよ」と言われて理解できなかった経験はないでしょうか?Figmaは、UI設計における構造的な概念(オートレイアウト、コンポーネント、バリアントなど)を備えており、開発とデザインの橋渡し役として機能します。
エンジニアがFigmaを扱えることで、デザイナーとのやりとりも非常にスムーズになります。伝達コストが減ることで、「デザインデータの解釈違い」「差し戻しによる手戻り」など、開発現場でありがちな問題を減らせます。
3. 修正依頼を自分で処理できるようになる
ちょっとした修正、例えば「このテキストを太字にする」「アイコンを10px右にずらす」などは、いちいちデザイナーに依頼するよりも、Figmaを開いて自分で変更確認できた方が早いです。
もちろん本番のデザインを勝手に書き換えることは推奨されませんが、クローンを作って挙動をシミュレートしたり、修正内容を明示的に共有したりできるようになると、スピード感のある開発が実現します。
4. デザインからCSSや値を正確に読み取れる
Figmaは、CSS情報(フォントサイズ、カラーコード、ボックスシャドウなど)をインスペクトモードで確認できます。これにより、スタイルの再現性が非常に高くなります。
特に、色やフォントの一貫性を担保したいときや、複雑なマージン設計の解析が必要なときに、Figmaを理解していることは大きなアドバンテージになります。
5. UI品質への感度が上がる
Figmaを日常的に使うことで、「あれ、このボタンのサイズ、他とズレてるな」といった微細なズレや違和感に気付く力が養われます。これは単なる視覚の訓練というより、“UI全体の設計思想を読む”力です。
この感度が育つと、設計の一貫性を保ちながら、ユーザー体験を損なわない改善提案ができるようになります。
Figmaは“開発のツール”でもある
Figmaは単なるデザインツールではなく、開発とデザインの接続点であり、エンジニアにとっても重要な「プロジェクト理解ツール」だと私は思っています。
「デザイナーが作ったものを再現する」という受け身の姿勢から、「UIの品質をともに作り上げる」立場へと、エンジニアのあり方は進化しています。Figmaを使いこなすことは、その第一歩なのではないでしょうか。
もし、まだFigmaに抵抗感がある方がいれば、まずは自分のプロジェクトのデザインデータを“触ってみる”ことから始めてみてください。意外とシンプルで、楽しい世界が広がっているかもしれません。