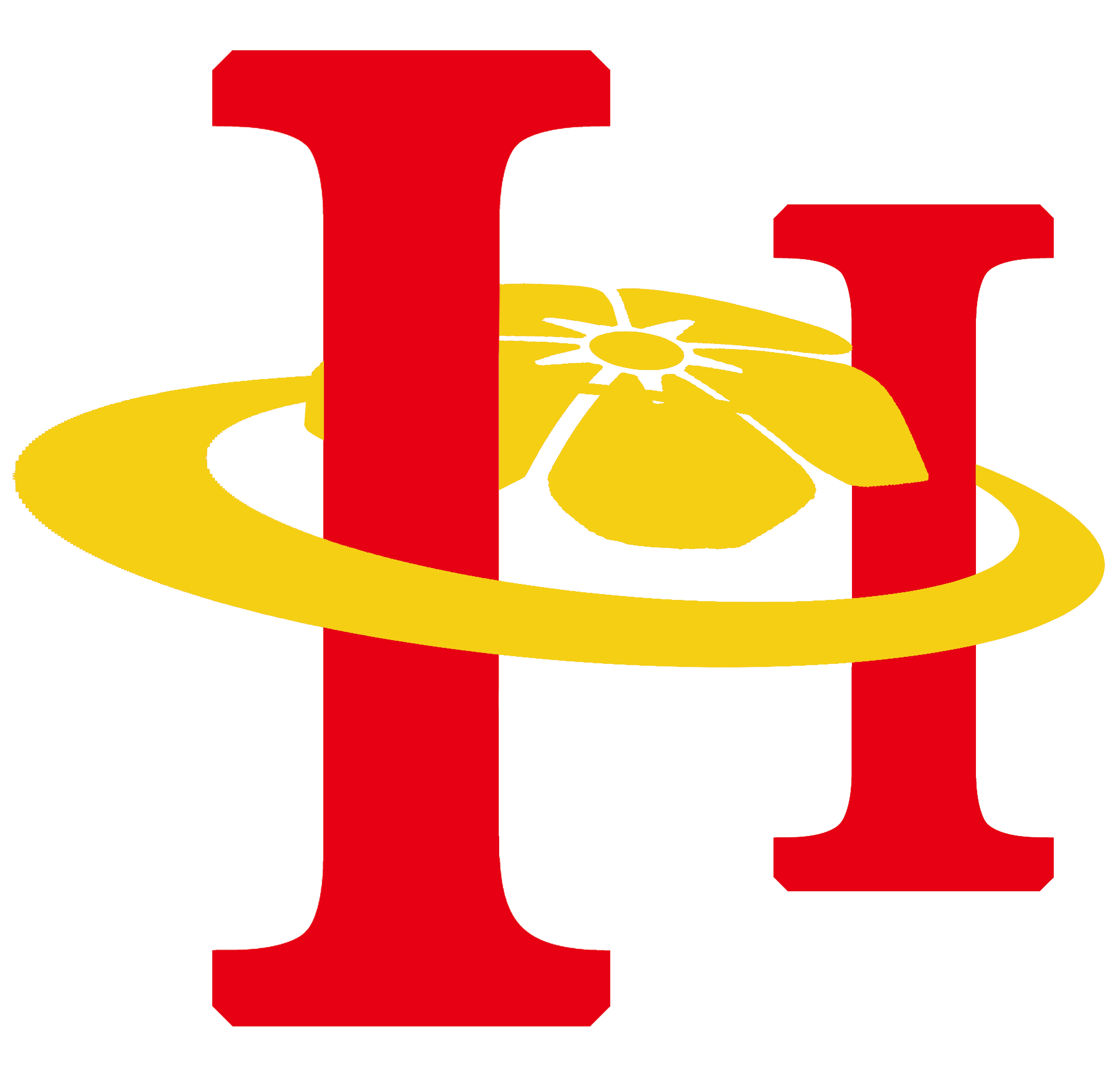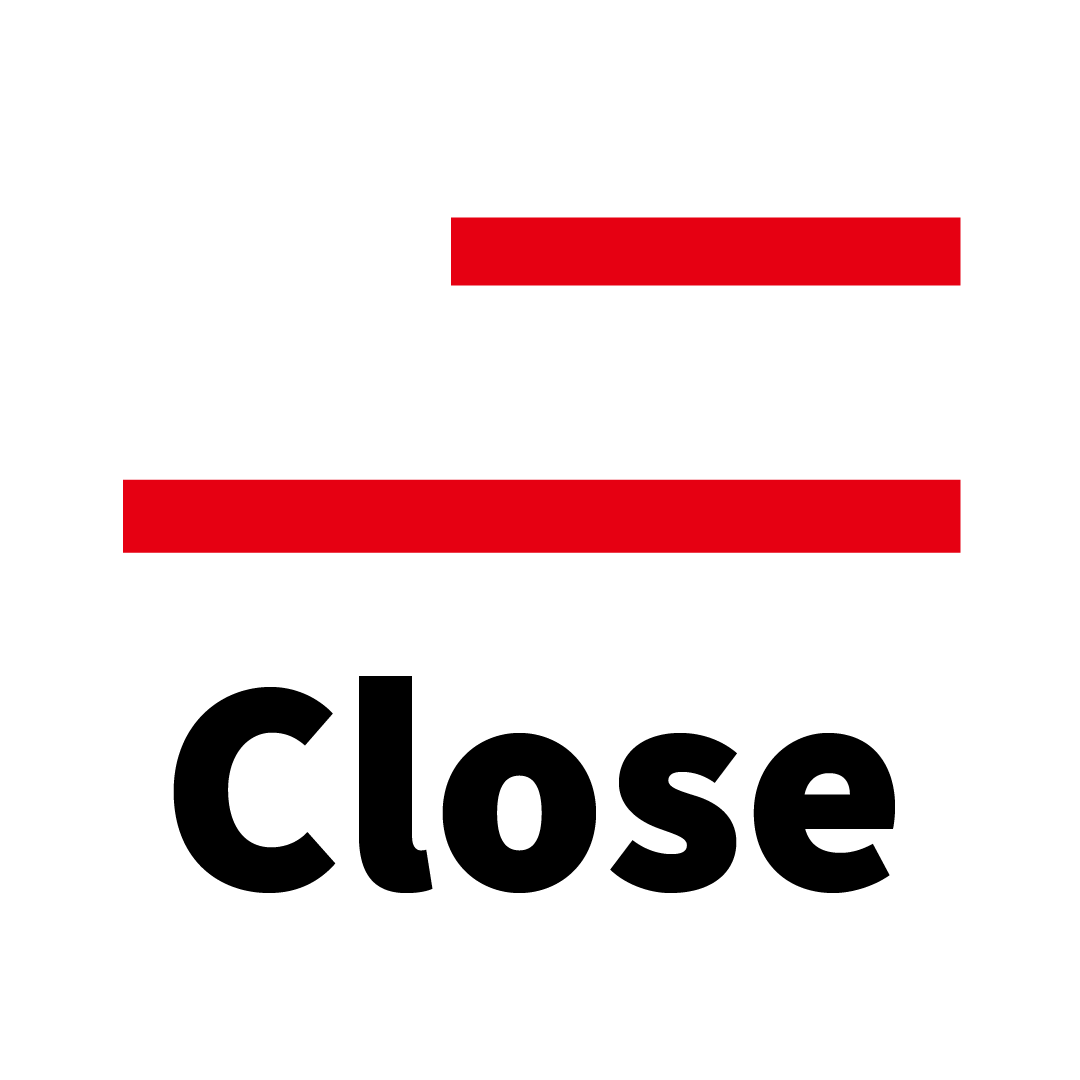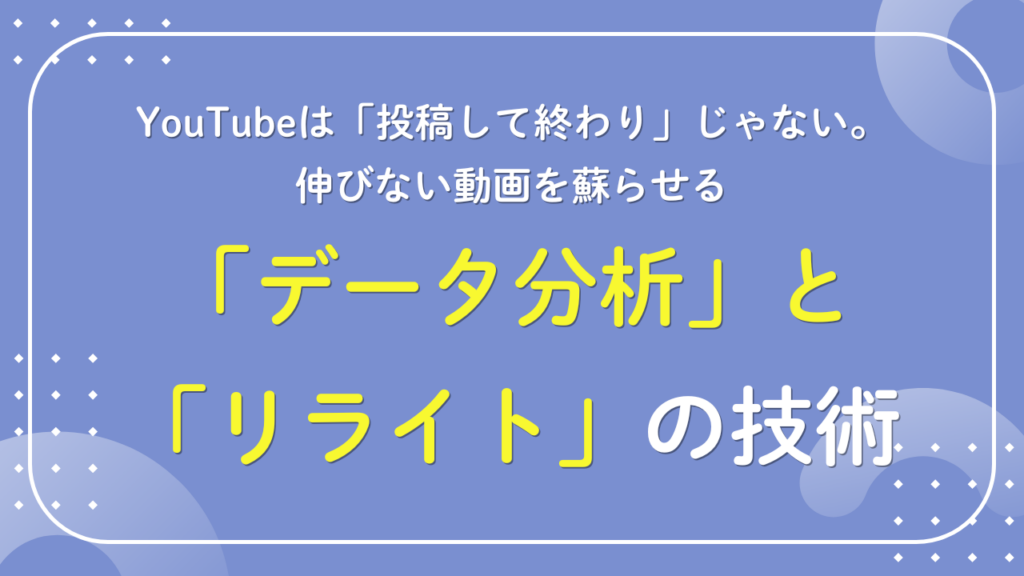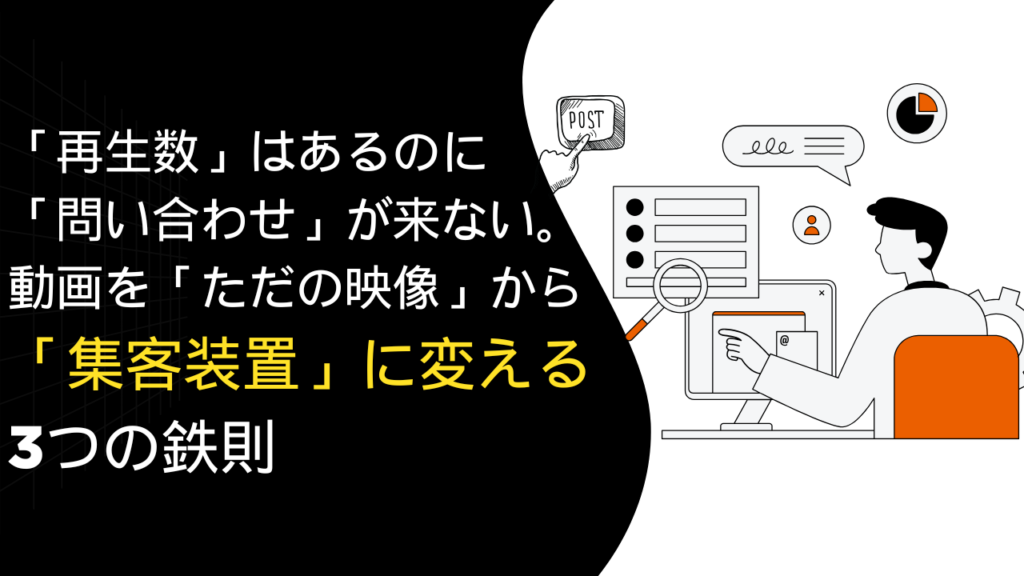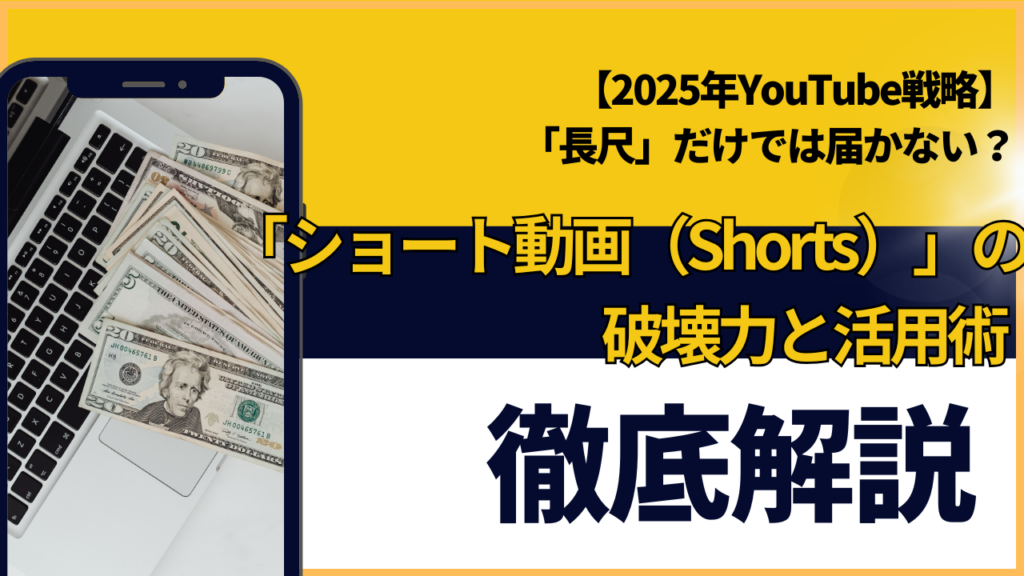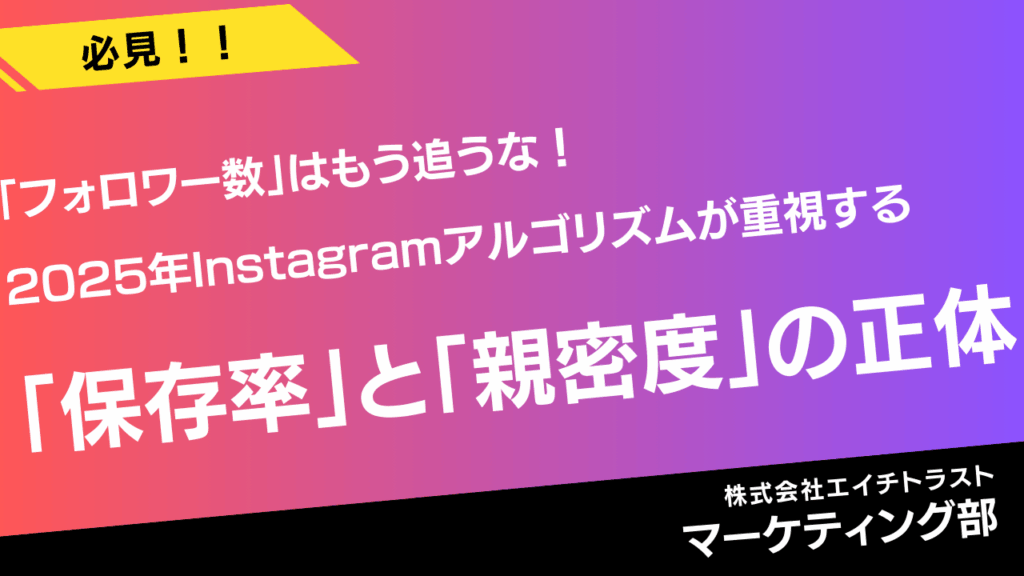モダンフロントエンド開発の「設計力」とは何か?-エンジニアY-

「設計」と聞くと、バックエンドのアーキテクチャやDB設計を想像する人も多いかもしれません。
しかし、フロントエンドの世界でも「設計力」はプロダクトの品質と生産性に直結する非常に重要なスキルです。
今回は、モダンなフロントエンド開発における「設計力」について、自分の経験も交えつつ掘り下げてみたいと思います。
1. 設計=ファイル構成ではない
React や Vue などのコンポーネントベースのフレームワークが主流になり、開発現場では「Atomic Design」「ドメイン駆動設計(DDD)」などの設計思想も広がってきました。
ただし、「設計力がある」というのは、単にそれっぽいディレクトリ構造にすることではありません。
設計力とは、変化に強く、可読性が高く、保守しやすい構造を考える力。
将来の仕様変更やチーム拡大に「耐えられるコード」をどう書くかを考え抜く姿勢が問われます。
2. 設計の基本は「依存の方向」を意識すること
たとえば、以下のような構成があったとします。
cssコピーする編集するcomponents/
└ Button.tsx
pages/
└ Home.tsx
ここで Button が Home に依存する構造になっていたら、再利用性は損なわれ、設計としては不適切です。
フロントエンドにおける良い設計とは、
- 共通 → 特化 の方向で依存すること
- ロジック → UI の方向で責任を分離すること
- アプリケーション層 → プレゼンテーション層 という意識を持つこと
このような責務と依存の分離を考える力が設計力の根幹です。
3. 設計力がないと何が起こるか
- ページ数が増えるとコンポーネントの再利用が効かなくなる
- チーム開発でコードの意図が伝わらず、属人化が進む
- 小さな修正が全体に影響しやすくなり、開発速度が低下する
設計力がない状態のコードは、どこかしら「もろい」です。
後から修正するときに「どこに何が影響するか」が見えにくく、心理的コストも高くなります。
4. 設計は「最初に完璧に作るもの」ではない
誤解されがちですが、設計は一度決めて終わりではありません。
むしろ、プロジェクトの進行に合わせて「常に見直す」「壊す前提で組み立てる」くらいがちょうどいいです。
必要なのは「今の要件に合った最小限のルール」と「将来変更しやすい柔軟性」の両立。
そのためには以下のような視点が必要です。
- この構造はどの程度スケーラブルか?
- 同じパターンの画面があと10個増えたとき、運用に耐えられるか?
- 誰かが3ヶ月後に見ても理解できるか?
5. 設計力をどう鍛えるか?
- 他人の設計を読む(OSS・有名プロジェクト)
- 小規模でもいいので、設計→開発→リファクタを繰り返す
- DDD、Atomic Design、Clean Architecture など複数の考え方に触れる
- ペアプロやコードレビューで設計意図を言語化する癖をつける
設計力は、日々の開発の中で鍛えていく「筋トレ」に近いスキルです。
最後に
モダンなフロントエンドは、ライブラリや技術の進化とともに、設計の重要性もどんどん増しています。
「コードを書くだけ」から一歩踏み込んで、「設計する力」を意識することで、より良いプロダクトづくりにつながっていくはずです。
自分自身も、まだまだ設計の試行錯誤を重ねる日々。
これからも、チームやユーザーのために“良い設計”を目指していきたいと思います。

「設計」と聞くと、バックエンドのアーキテクチャやDB設計を想像する人も多いかもしれません。
しかし、フロントエンドの世界でも「設計力」はプロダクトの品質と生産性に直結する非常に重要なスキルです。
今回は、モダンなフロントエンド開発における「設計力」について、自分の経験も交えつつ掘り下げてみたいと思います。
1. 設計=ファイル構成ではない
React や Vue などのコンポーネントベースのフレームワークが主流になり、開発現場では「Atomic Design」「ドメイン駆動設計(DDD)」などの設計思想も広がってきました。
ただし、「設計力がある」というのは、単にそれっぽいディレクトリ構造にすることではありません。
設計力とは、変化に強く、可読性が高く、保守しやすい構造を考える力。
将来の仕様変更やチーム拡大に「耐えられるコード」をどう書くかを考え抜く姿勢が問われます。
2. 設計の基本は「依存の方向」を意識すること
たとえば、以下のような構成があったとします。
cssコピーする編集するcomponents/
└ Button.tsx
pages/
└ Home.tsx
ここで Button が Home に依存する構造になっていたら、再利用性は損なわれ、設計としては不適切です。
フロントエンドにおける良い設計とは、
- 共通 → 特化 の方向で依存すること
- ロジック → UI の方向で責任を分離すること
- アプリケーション層 → プレゼンテーション層 という意識を持つこと
このような責務と依存の分離を考える力が設計力の根幹です。
3. 設計力がないと何が起こるか
- ページ数が増えるとコンポーネントの再利用が効かなくなる
- チーム開発でコードの意図が伝わらず、属人化が進む
- 小さな修正が全体に影響しやすくなり、開発速度が低下する
設計力がない状態のコードは、どこかしら「もろい」です。
後から修正するときに「どこに何が影響するか」が見えにくく、心理的コストも高くなります。
4. 設計は「最初に完璧に作るもの」ではない
誤解されがちですが、設計は一度決めて終わりではありません。
むしろ、プロジェクトの進行に合わせて「常に見直す」「壊す前提で組み立てる」くらいがちょうどいいです。
必要なのは「今の要件に合った最小限のルール」と「将来変更しやすい柔軟性」の両立。
そのためには以下のような視点が必要です。
- この構造はどの程度スケーラブルか?
- 同じパターンの画面があと10個増えたとき、運用に耐えられるか?
- 誰かが3ヶ月後に見ても理解できるか?
5. 設計力をどう鍛えるか?
- 他人の設計を読む(OSS・有名プロジェクト)
- 小規模でもいいので、設計→開発→リファクタを繰り返す
- DDD、Atomic Design、Clean Architecture など複数の考え方に触れる
- ペアプロやコードレビューで設計意図を言語化する癖をつける
設計力は、日々の開発の中で鍛えていく「筋トレ」に近いスキルです。
最後に
モダンなフロントエンドは、ライブラリや技術の進化とともに、設計の重要性もどんどん増しています。
「コードを書くだけ」から一歩踏み込んで、「設計する力」を意識することで、より良いプロダクトづくりにつながっていくはずです。
自分自身も、まだまだ設計の試行錯誤を重ねる日々。
これからも、チームやユーザーのために“良い設計”を目指していきたいと思います。