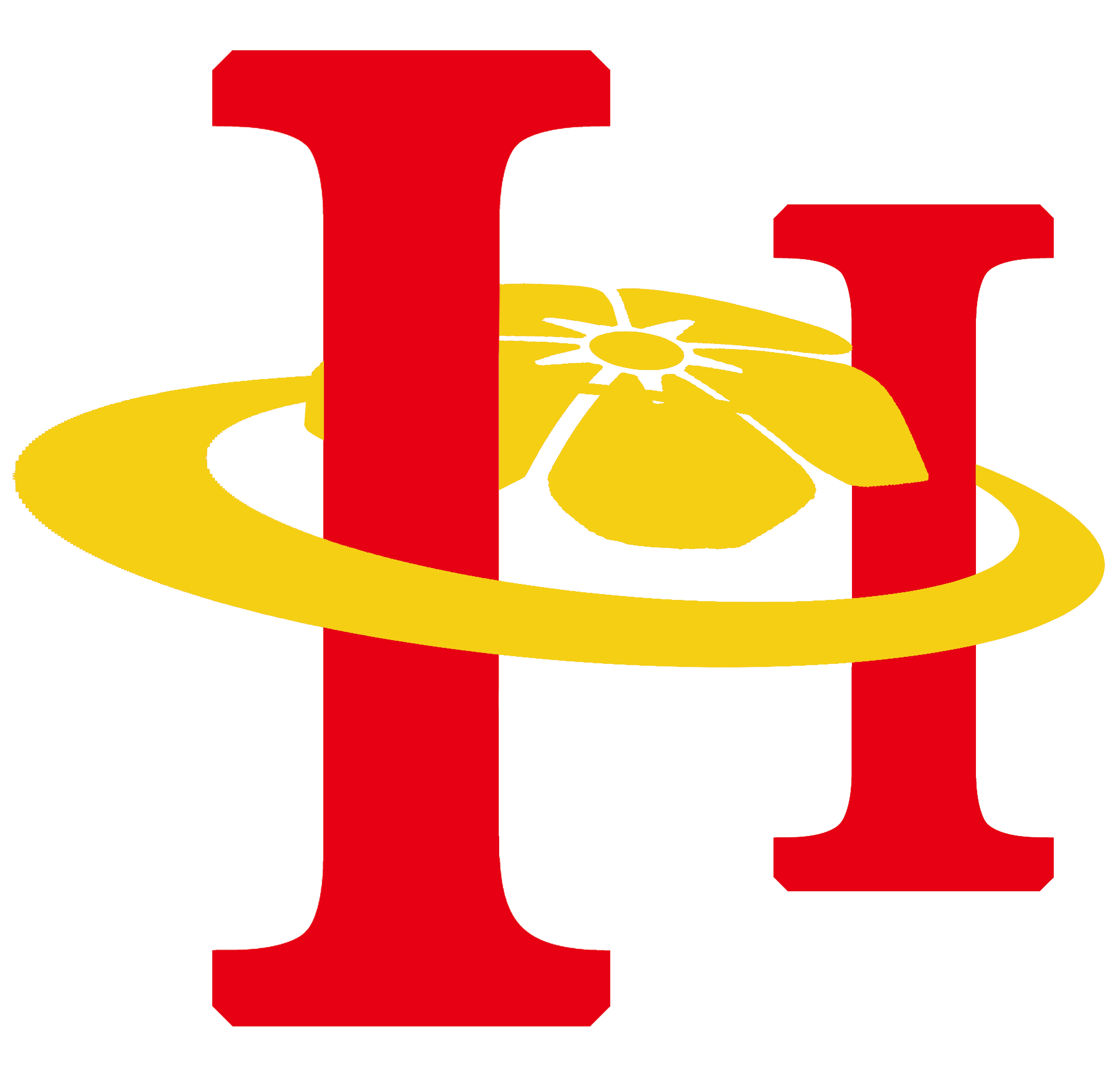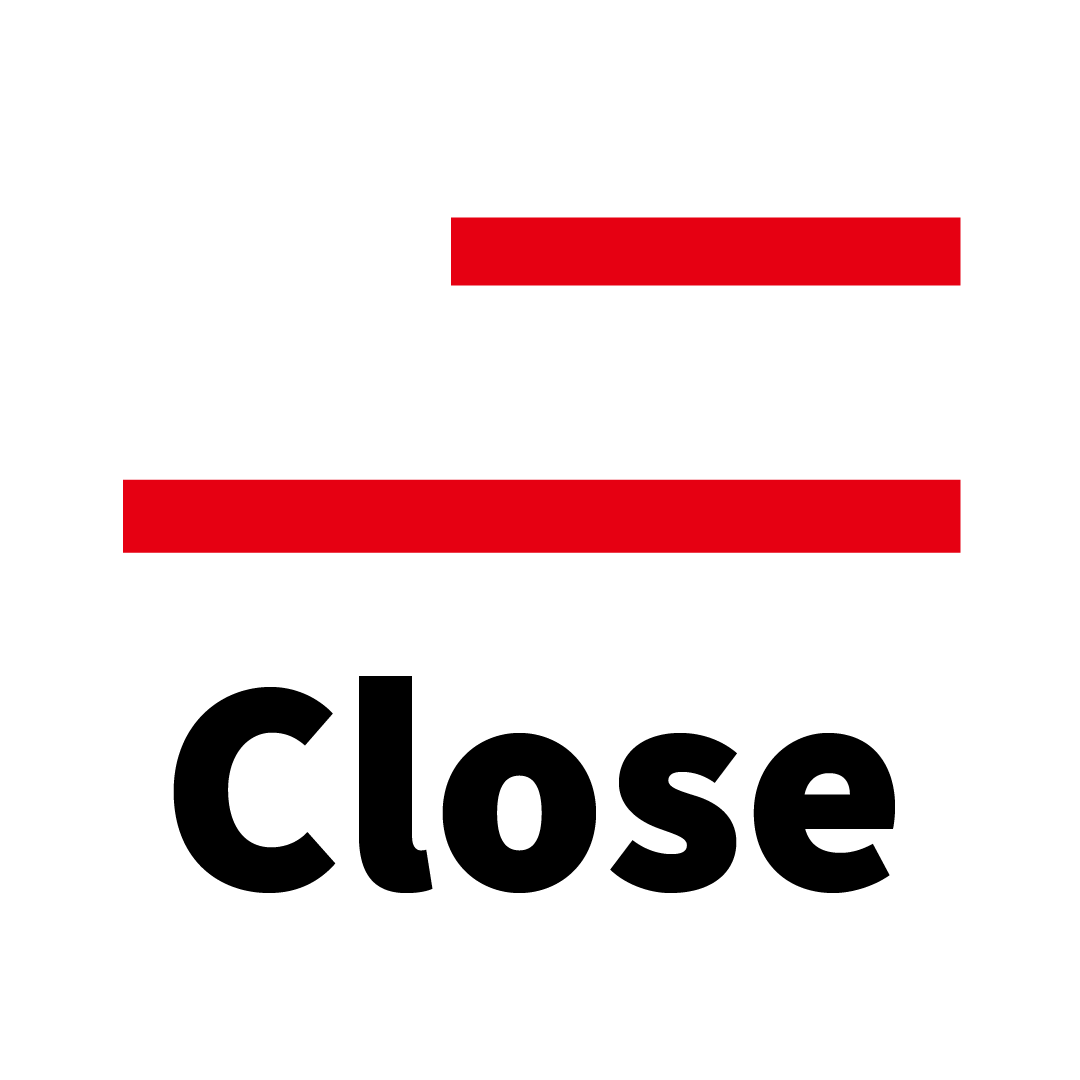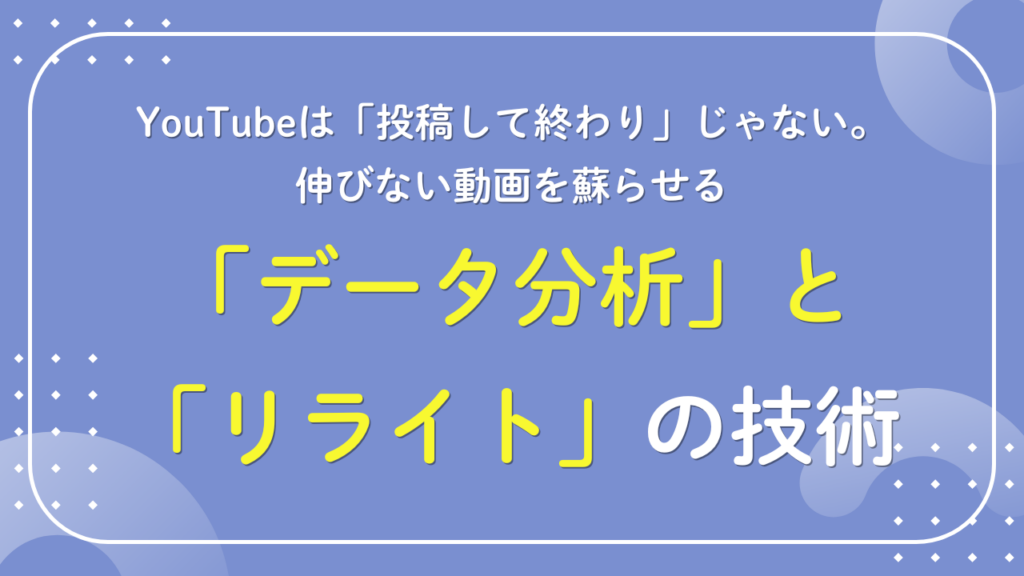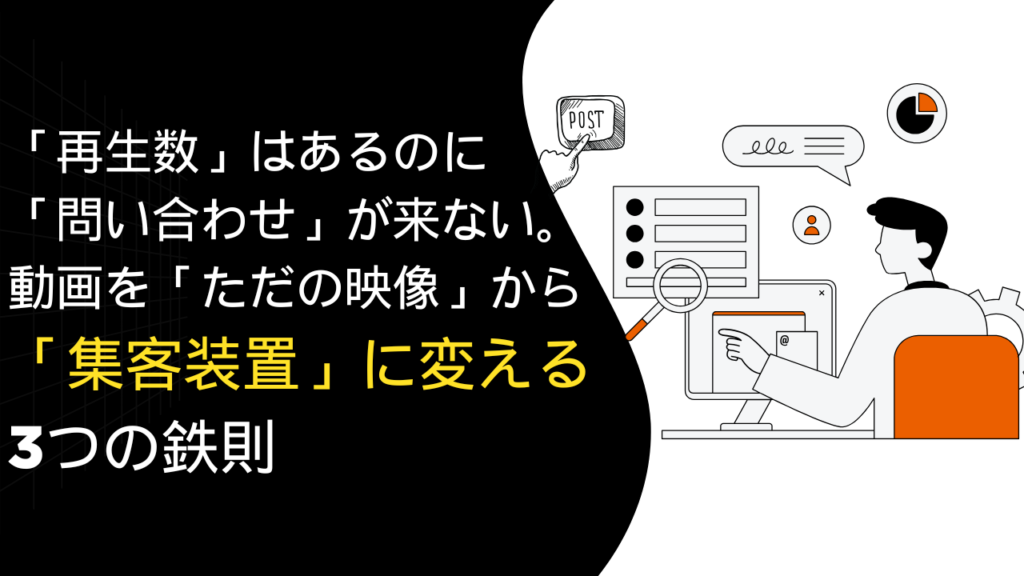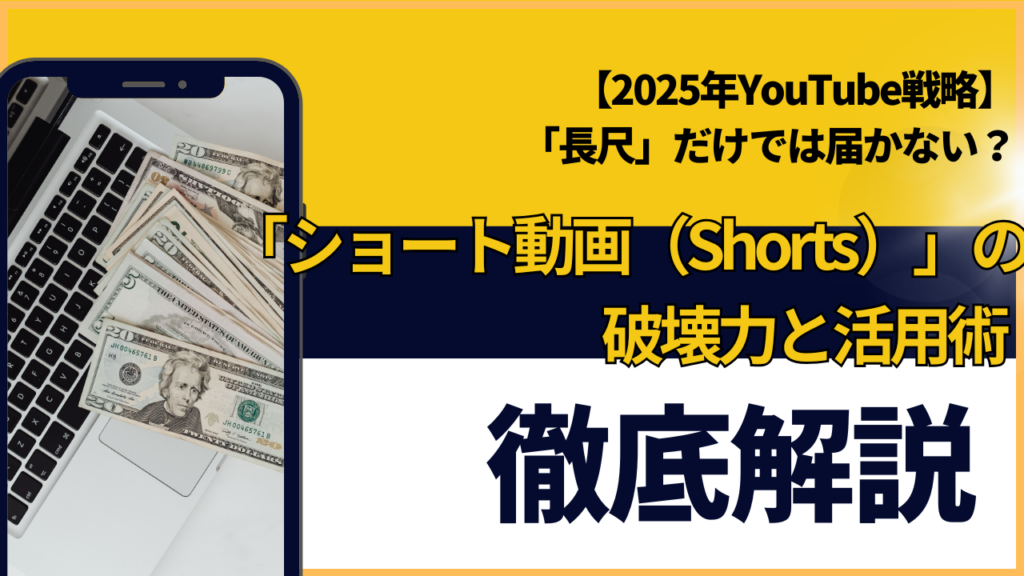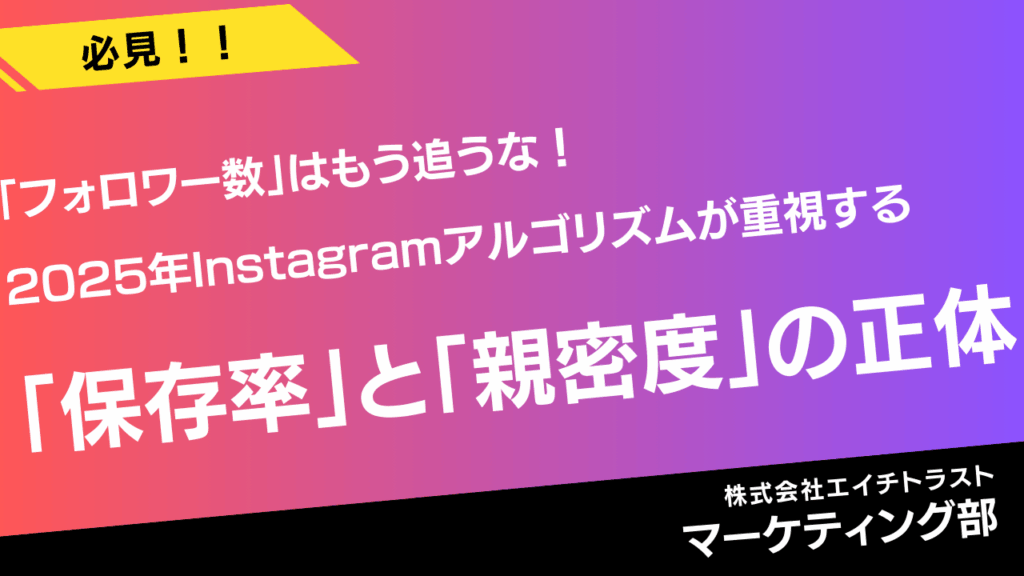“動くサイト”では成果が出ない?設計力が支えるコンバージョン導線-マーケティング部T-
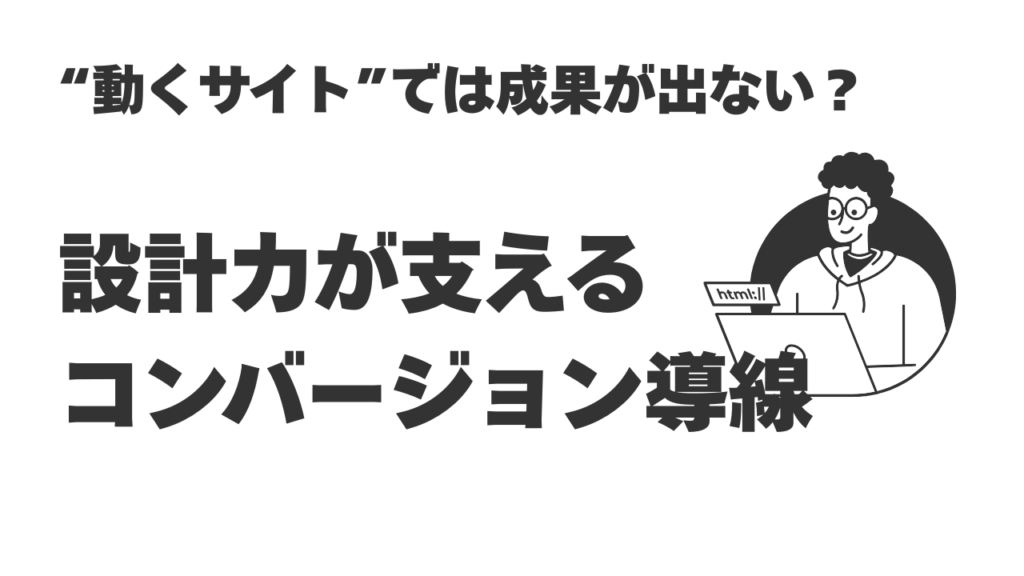
近年、WebサイトやLPのトレンドはめまぐるしく変化しています。モーションやアニメーションを駆使した、視覚的にリッチな「動くサイト」もその一つ。しかし、そうした表層的な“見た目”の進化に反して、マーケティング部として感じる課題があります。
「PVは取れてもCVしない」
「離脱率は減っていない」
「GAを見ても導線が迷子」
そう、成果につながる“設計力”が不足しているサイトが増えているのです。
設計力とは「意図を持って構造をつくること」
我々マーケティング部は、Webサイトを「コンバージョン装置」だと考えます。プロモーションを展開するにも、広告を流すにも、CVの着地点が設計されていなければ意味がありません。
ここで必要なのが、UIでもUXでもないその“間”にある設計力です。
具体的には、以下のような設計思考です。
- ユーザーの行動シナリオをもとに導線を設計しているか
- 各要素(ボタン・リンク・フォーム)が適切なタイミングで出現するか
- スクロールやクリックが「次のステップ」を自然に促す構成になっているか
- UIコンポーネントとコンテンツの関係性が整理されているか
こうした“構造的意図”が無いまま、ただ動いているだけのサイトは、マーケにとっては「中身のない箱」です。
表層だけでは、ユーザーは動かない
とにかくアニメーションを加えておけば「今っぽく」見える。そんな制作現場の声も少なくありません。しかし、動きが過剰なUIはユーザーの注意を拡散させ、導線を見えにくくする要因にもなります。
また、デザインの先鋭化が進むと、マーケティング部が求める「測定」「改善」のPDCAが回しづらくなることも。
たとえば、ABテストのしづらい構造、分析タグが入れにくいレイアウト、CMSとの親和性が低い構築方法などは、運用フェーズに入ってから大きな壁になります。
成果を追うマーケチームにとっては、動くより“動かす”構造が重要なのです。
設計力をマーケ施策に活かすために
マーケティング部として、制作チームに伝えたいことがあります。
それは、「設計段階からマーケを巻き込んでほしい」ということ。
私たちは、ユーザーのペルソナやカスタマージャーニーの設計、KPI設計、広告の流入元やキャンペーンの流れなど、成果を出すための情報を多く持っています。その情報をもとに、ファーストビューからコンバージョンポイントまで、構造的に正しい流れを作る必要があります。
制作とマーケが分断されていると、「いい感じに動くけど成果に繋がらないサイト」が出来上がってしまうのです。
まとめ:設計力は、成果の前提条件
今後のWebマーケティングは、見た目や流行だけでなく、「構造=設計力」こそが差を生むポイントになると私たちは考えています。
動きのある演出はもちろん大切ですが、それが「意図を持って配置された導線の中にある」ことが、最終的に成果へとつながるのです。
マーケティング部としては、設計力のあるWeb制作チームとともに、意図あるサイトを設計し、成果に直結する動線を構築していきたいと考えています。
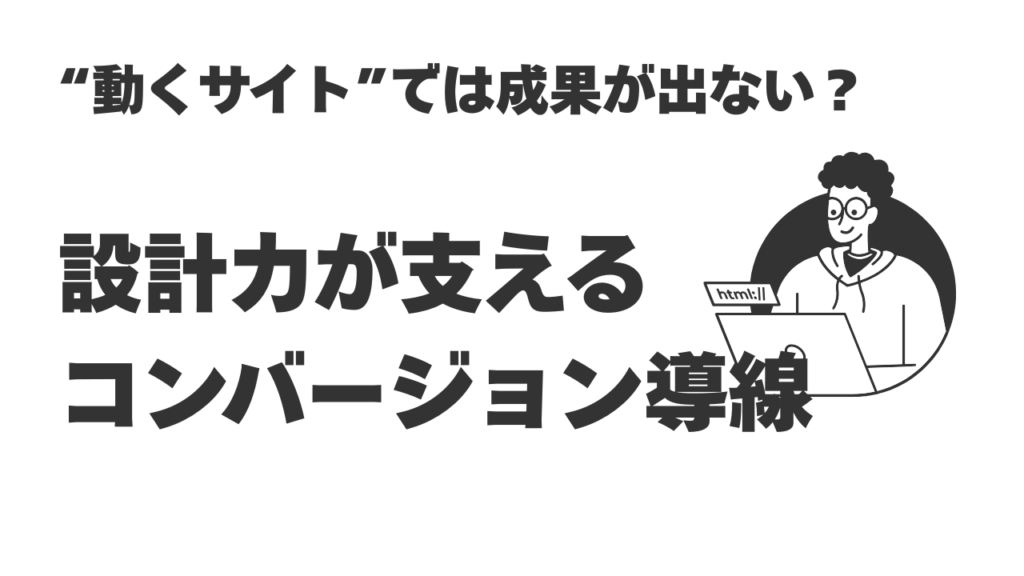
近年、WebサイトやLPのトレンドはめまぐるしく変化しています。モーションやアニメーションを駆使した、視覚的にリッチな「動くサイト」もその一つ。しかし、そうした表層的な“見た目”の進化に反して、マーケティング部として感じる課題があります。
「PVは取れてもCVしない」
「離脱率は減っていない」
「GAを見ても導線が迷子」
そう、成果につながる“設計力”が不足しているサイトが増えているのです。
設計力とは「意図を持って構造をつくること」
我々マーケティング部は、Webサイトを「コンバージョン装置」だと考えます。プロモーションを展開するにも、広告を流すにも、CVの着地点が設計されていなければ意味がありません。
ここで必要なのが、UIでもUXでもないその“間”にある設計力です。
具体的には、以下のような設計思考です。
- ユーザーの行動シナリオをもとに導線を設計しているか
- 各要素(ボタン・リンク・フォーム)が適切なタイミングで出現するか
- スクロールやクリックが「次のステップ」を自然に促す構成になっているか
- UIコンポーネントとコンテンツの関係性が整理されているか
こうした“構造的意図”が無いまま、ただ動いているだけのサイトは、マーケにとっては「中身のない箱」です。
表層だけでは、ユーザーは動かない
とにかくアニメーションを加えておけば「今っぽく」見える。そんな制作現場の声も少なくありません。しかし、動きが過剰なUIはユーザーの注意を拡散させ、導線を見えにくくする要因にもなります。
また、デザインの先鋭化が進むと、マーケティング部が求める「測定」「改善」のPDCAが回しづらくなることも。
たとえば、ABテストのしづらい構造、分析タグが入れにくいレイアウト、CMSとの親和性が低い構築方法などは、運用フェーズに入ってから大きな壁になります。
成果を追うマーケチームにとっては、動くより“動かす”構造が重要なのです。
設計力をマーケ施策に活かすために
マーケティング部として、制作チームに伝えたいことがあります。
それは、「設計段階からマーケを巻き込んでほしい」ということ。
私たちは、ユーザーのペルソナやカスタマージャーニーの設計、KPI設計、広告の流入元やキャンペーンの流れなど、成果を出すための情報を多く持っています。その情報をもとに、ファーストビューからコンバージョンポイントまで、構造的に正しい流れを作る必要があります。
制作とマーケが分断されていると、「いい感じに動くけど成果に繋がらないサイト」が出来上がってしまうのです。
まとめ:設計力は、成果の前提条件
今後のWebマーケティングは、見た目や流行だけでなく、「構造=設計力」こそが差を生むポイントになると私たちは考えています。
動きのある演出はもちろん大切ですが、それが「意図を持って配置された導線の中にある」ことが、最終的に成果へとつながるのです。
マーケティング部としては、設計力のあるWeb制作チームとともに、意図あるサイトを設計し、成果に直結する動線を構築していきたいと考えています。