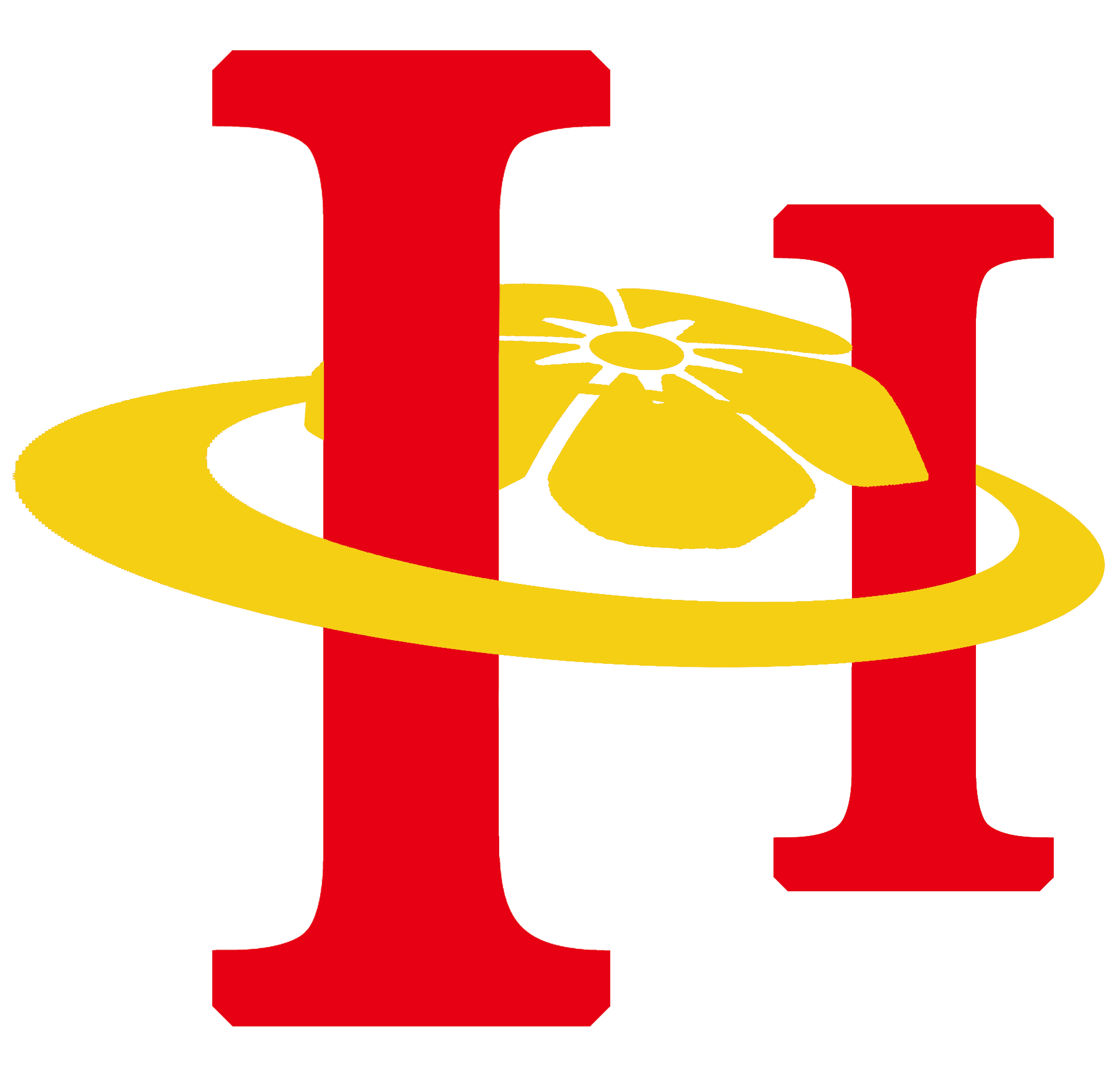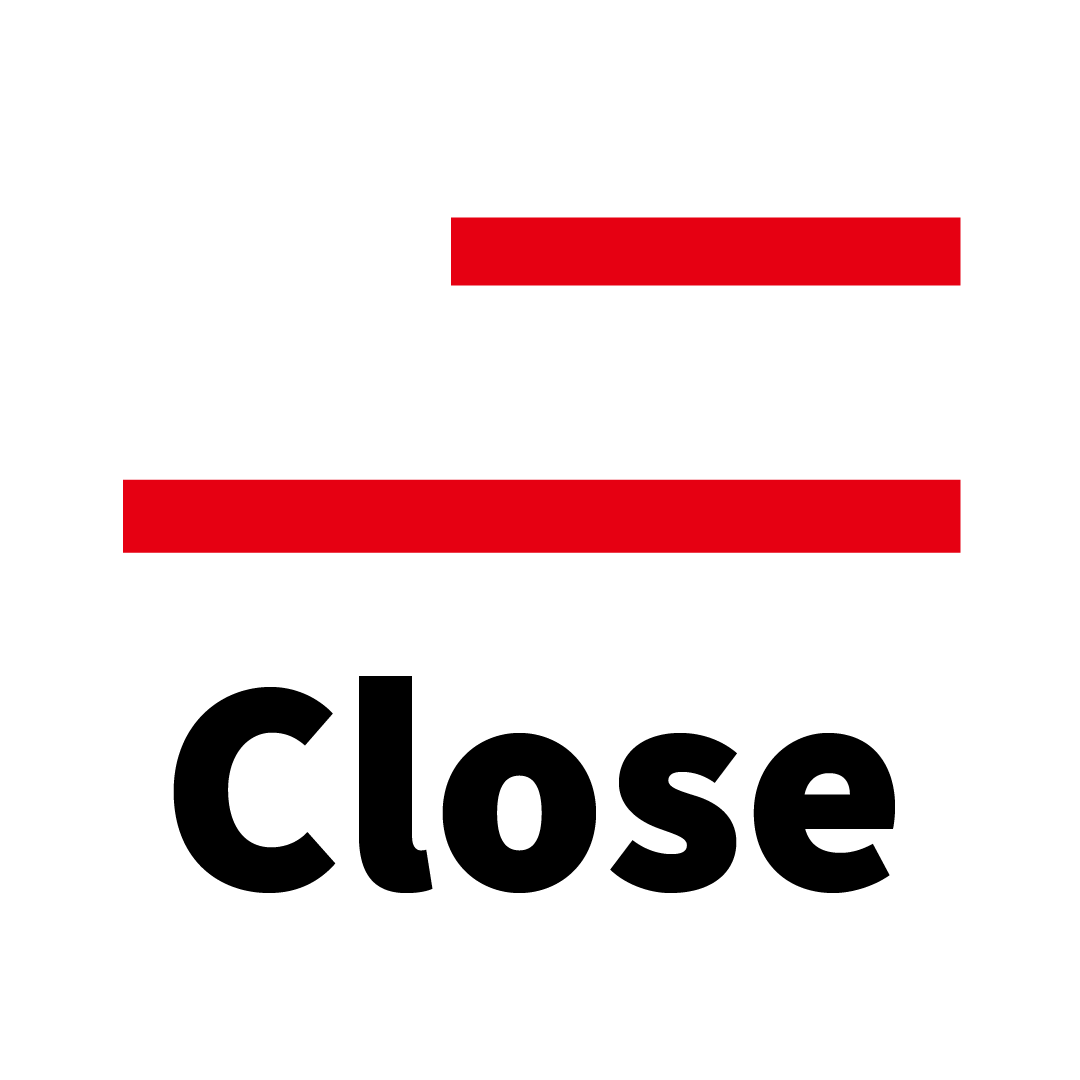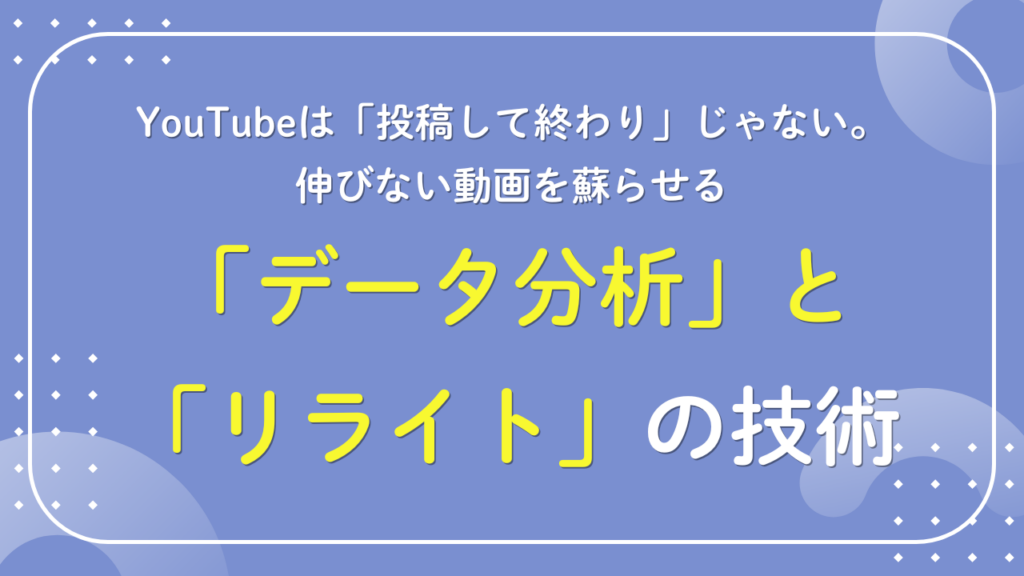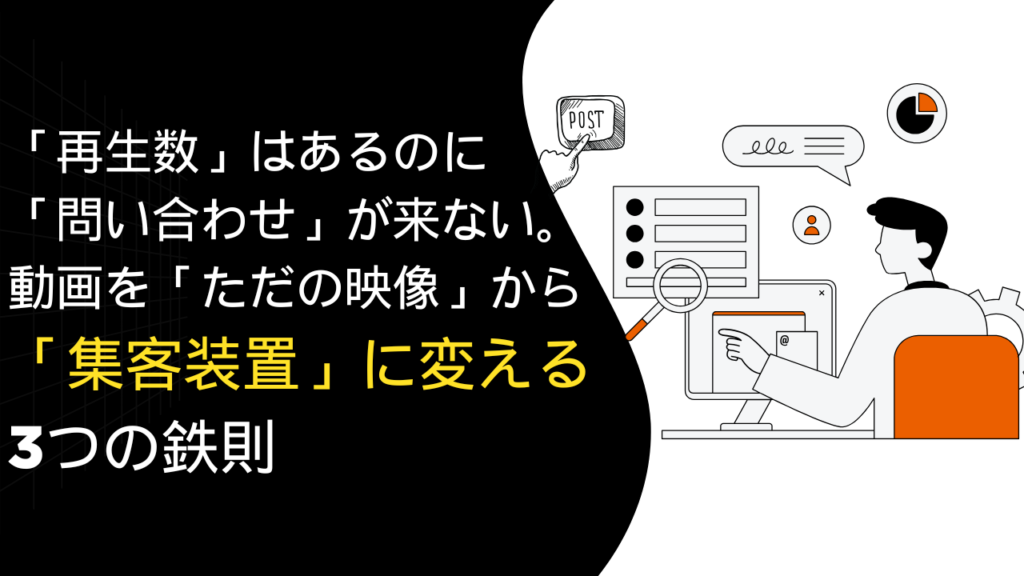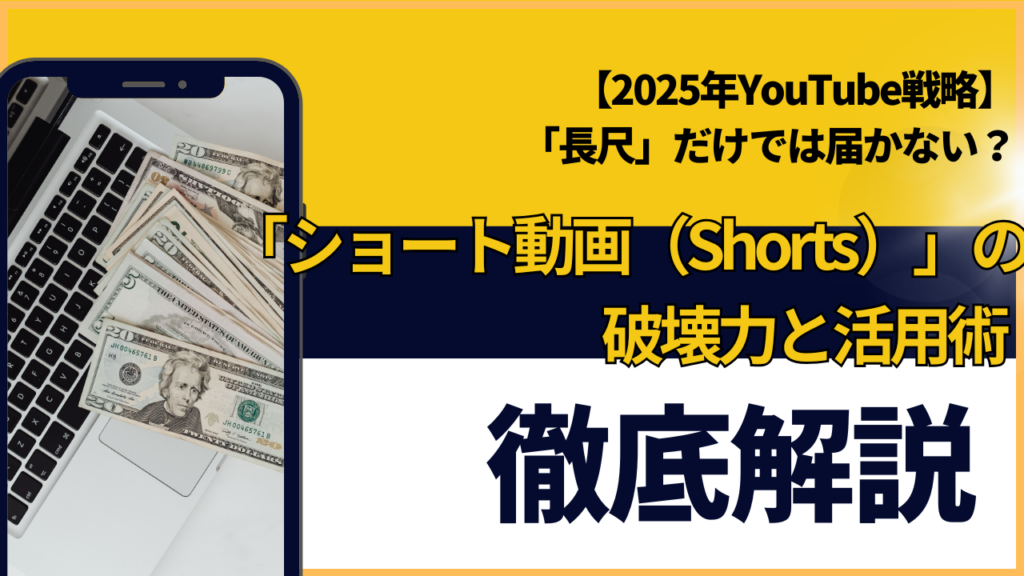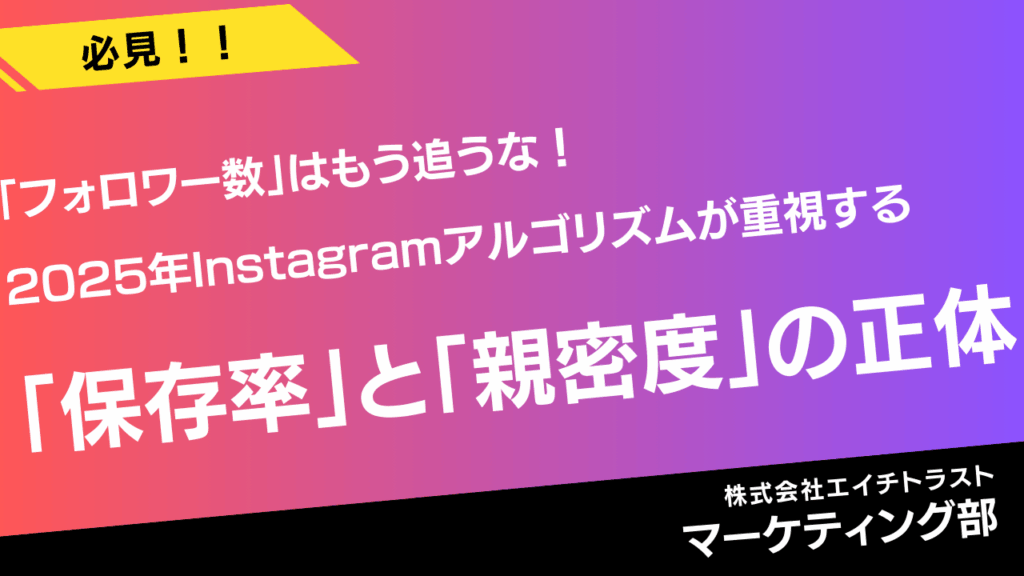なぜ設計の浅いサイトは離脱されるのか?UX観点で見直す開発の要-マーケティング部T-
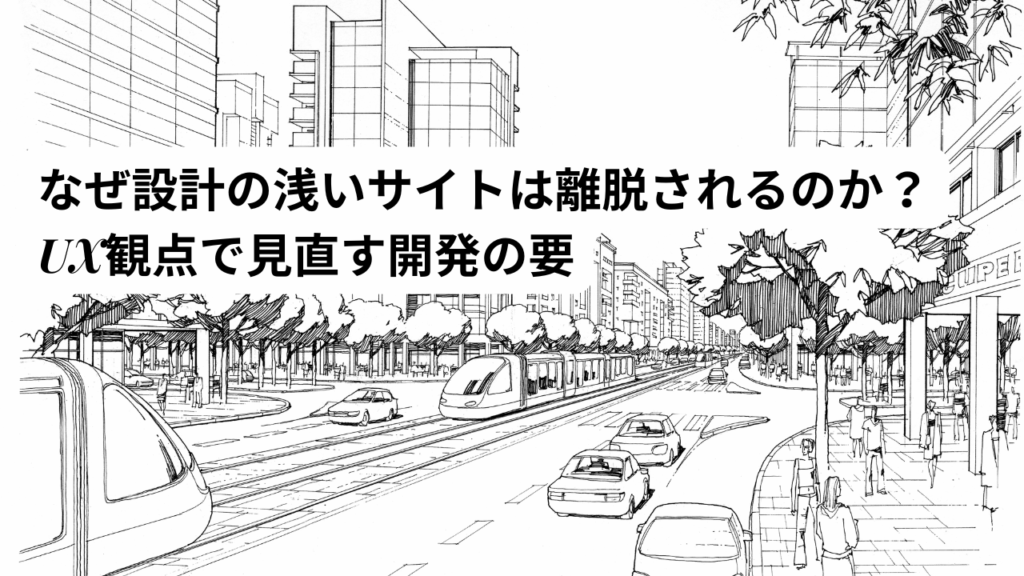
Webサイトの制作やリニューアルをする際、「見た目」や「機能性」ばかりに目がいっていないでしょうか。もちろんそれらは重要です。しかし、それらを“どう組み合わせるか”、つまり「設計」の深さが、実はユーザーの離脱率やコンバージョンに大きく影響しています。
マーケティング部として日々成果を追うなかで、「思ったより数値が伸びない」「広告流入はあるのにCVに繋がらない」という状況に直面することがあります。その原因を辿ると、意外と多いのが“設計の浅さ”です。
ユーザーの脳内フローを考慮しているか?
UX(ユーザーエクスペリエンス)の観点で重要なのは、ユーザーが訪れた瞬間に「自分に関係のある内容だ」と直感できることです。これはデザインでもコンテンツでもなく、設計そのものの力です。
たとえば、広告経由で「資料請求」に興味があって訪れたユーザーが、ファーストビューに全く関係ないキャンペーン情報を目にしたらどうでしょうか。目的とのズレに違和感を覚え、すぐに離脱してしまうでしょう。
サイトは“整理整頓”されているだけでは不十分です。ユーザーの目的に応じて「最短でたどり着ける動線設計」が必要です。そのためには、ユーザーが次に何を考え、どこを見ようとするかを先回りして設計することが欠かせません。
コンテンツの“順番”がUXを決める
マーケティング施策では「何を伝えるか」に注力する傾向がありますが、「どう伝えるか」「どの順番で見せるか」は同じくらい重要です。
設計が浅いと、各コンテンツが“ただあるだけ”になり、ユーザーにとってはノイズになります。これは、情報の過不足ではなく“配置の問題”です。UIとして見やすくても、UXとしては迷いを生みやすい状態です。
逆に、設計の深いサイトはコンテンツに「意味のある順番」があります。ユーザーは自然にスクロールしながら納得を重ね、最終的なアクションに至ります。
表層ではなく“構造”がブランド体験を決める
「うちのブランドらしいビジュアルにしたい」「柔らかい雰囲気で統一したい」など、ビジュアル面に注目することは多いですが、ブランド体験を支えているのは構造=設計です。
ユーザーは一つ一つの要素ではなく、サイト全体の体験からブランド印象を形成します。その体験のなかに、“余白の意味”や“行動を促すタイミング”といった設計の工夫が染み込んでいれば、深く記憶に残るブランド体験が生まれます。
設計に“マーケ視点”を取り入れる
Webサイトの設計は、デザイナーや開発者の仕事だと思われがちですが、本来はマーケティングの文脈と密接に関係しています。
・ユーザーはどこから来て、どんな状態でサイトに入るのか
・どのような心理の流れを辿って、どこでアクションを起こすのか
・コンバージョン後の満足度はどうか
これらを俯瞰し、設計の段階からマーケティング視点を反映させることで、離脱の少ない、成果の出るサイトがつくれます。
まとめ:設計は“目に見えないUX”の基盤
Webサイトにおいて「設計の深さ」は目に見えません。しかし、ユーザーはその“違和感”を敏感に察知します。クリック率や回遊率など、数値で現れる問題の多くは設計に起因しています。
成果が思うように出ないとき、UIやデザインの変更ではなく、まずはUXの観点から設計を見直すこと。それが、マーケティング部として、今後より良い成果を上げるための第一歩になると考えています。
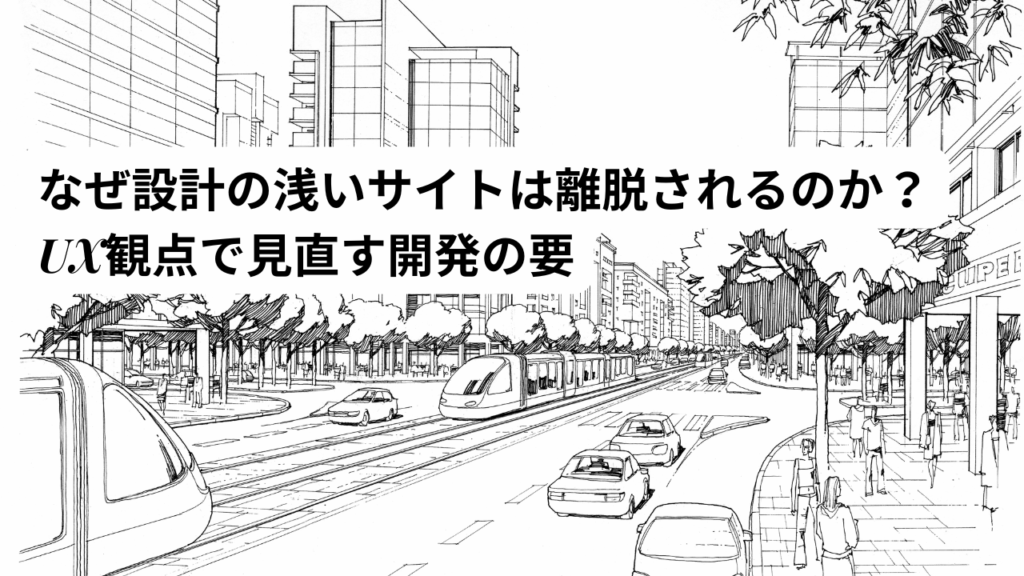
Webサイトの制作やリニューアルをする際、「見た目」や「機能性」ばかりに目がいっていないでしょうか。もちろんそれらは重要です。しかし、それらを“どう組み合わせるか”、つまり「設計」の深さが、実はユーザーの離脱率やコンバージョンに大きく影響しています。
マーケティング部として日々成果を追うなかで、「思ったより数値が伸びない」「広告流入はあるのにCVに繋がらない」という状況に直面することがあります。その原因を辿ると、意外と多いのが“設計の浅さ”です。
ユーザーの脳内フローを考慮しているか?
UX(ユーザーエクスペリエンス)の観点で重要なのは、ユーザーが訪れた瞬間に「自分に関係のある内容だ」と直感できることです。これはデザインでもコンテンツでもなく、設計そのものの力です。
たとえば、広告経由で「資料請求」に興味があって訪れたユーザーが、ファーストビューに全く関係ないキャンペーン情報を目にしたらどうでしょうか。目的とのズレに違和感を覚え、すぐに離脱してしまうでしょう。
サイトは“整理整頓”されているだけでは不十分です。ユーザーの目的に応じて「最短でたどり着ける動線設計」が必要です。そのためには、ユーザーが次に何を考え、どこを見ようとするかを先回りして設計することが欠かせません。
コンテンツの“順番”がUXを決める
マーケティング施策では「何を伝えるか」に注力する傾向がありますが、「どう伝えるか」「どの順番で見せるか」は同じくらい重要です。
設計が浅いと、各コンテンツが“ただあるだけ”になり、ユーザーにとってはノイズになります。これは、情報の過不足ではなく“配置の問題”です。UIとして見やすくても、UXとしては迷いを生みやすい状態です。
逆に、設計の深いサイトはコンテンツに「意味のある順番」があります。ユーザーは自然にスクロールしながら納得を重ね、最終的なアクションに至ります。
表層ではなく“構造”がブランド体験を決める
「うちのブランドらしいビジュアルにしたい」「柔らかい雰囲気で統一したい」など、ビジュアル面に注目することは多いですが、ブランド体験を支えているのは構造=設計です。
ユーザーは一つ一つの要素ではなく、サイト全体の体験からブランド印象を形成します。その体験のなかに、“余白の意味”や“行動を促すタイミング”といった設計の工夫が染み込んでいれば、深く記憶に残るブランド体験が生まれます。
設計に“マーケ視点”を取り入れる
Webサイトの設計は、デザイナーや開発者の仕事だと思われがちですが、本来はマーケティングの文脈と密接に関係しています。
・ユーザーはどこから来て、どんな状態でサイトに入るのか
・どのような心理の流れを辿って、どこでアクションを起こすのか
・コンバージョン後の満足度はどうか
これらを俯瞰し、設計の段階からマーケティング視点を反映させることで、離脱の少ない、成果の出るサイトがつくれます。
まとめ:設計は“目に見えないUX”の基盤
Webサイトにおいて「設計の深さ」は目に見えません。しかし、ユーザーはその“違和感”を敏感に察知します。クリック率や回遊率など、数値で現れる問題の多くは設計に起因しています。
成果が思うように出ないとき、UIやデザインの変更ではなく、まずはUXの観点から設計を見直すこと。それが、マーケティング部として、今後より良い成果を上げるための第一歩になると考えています。