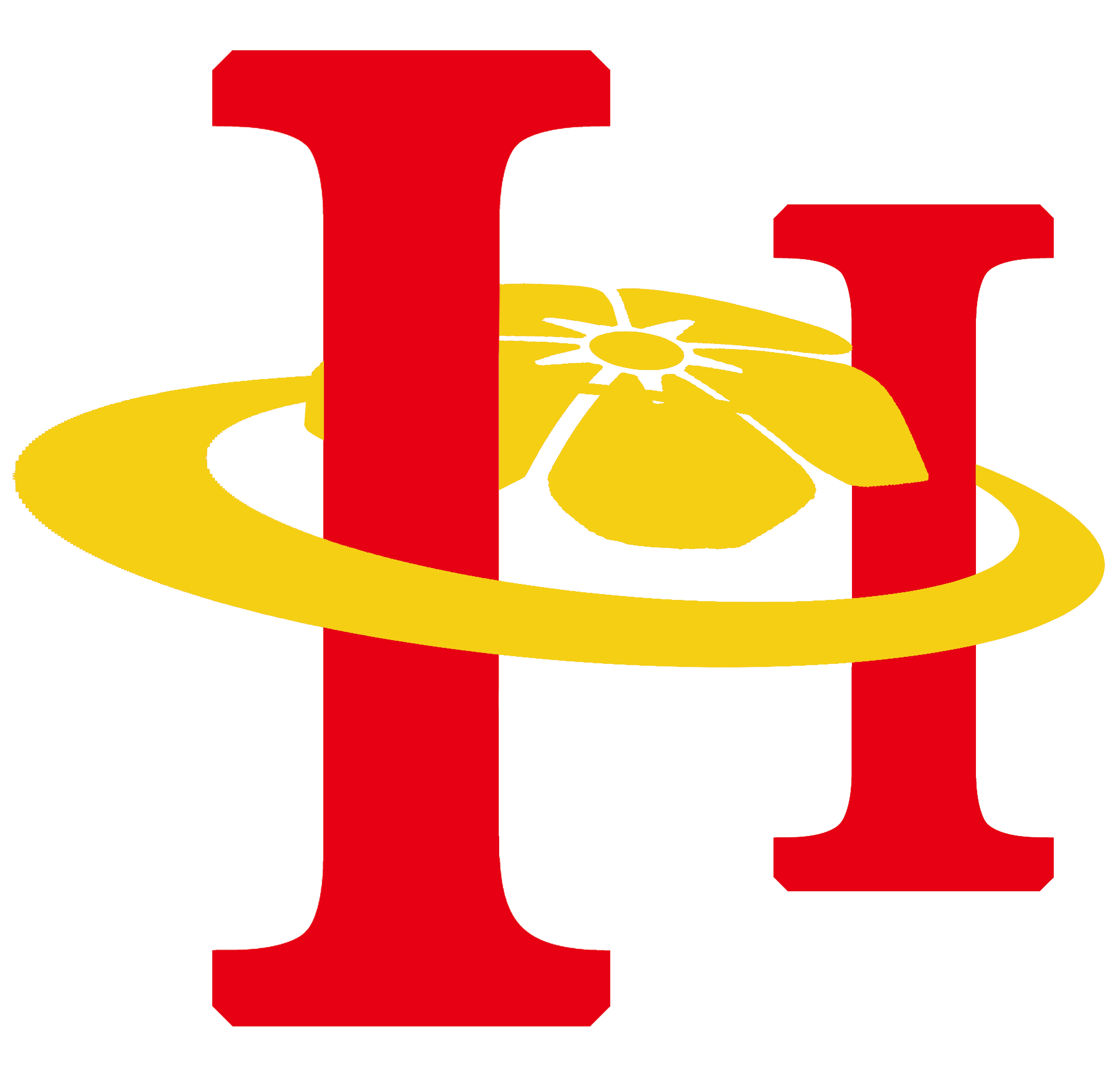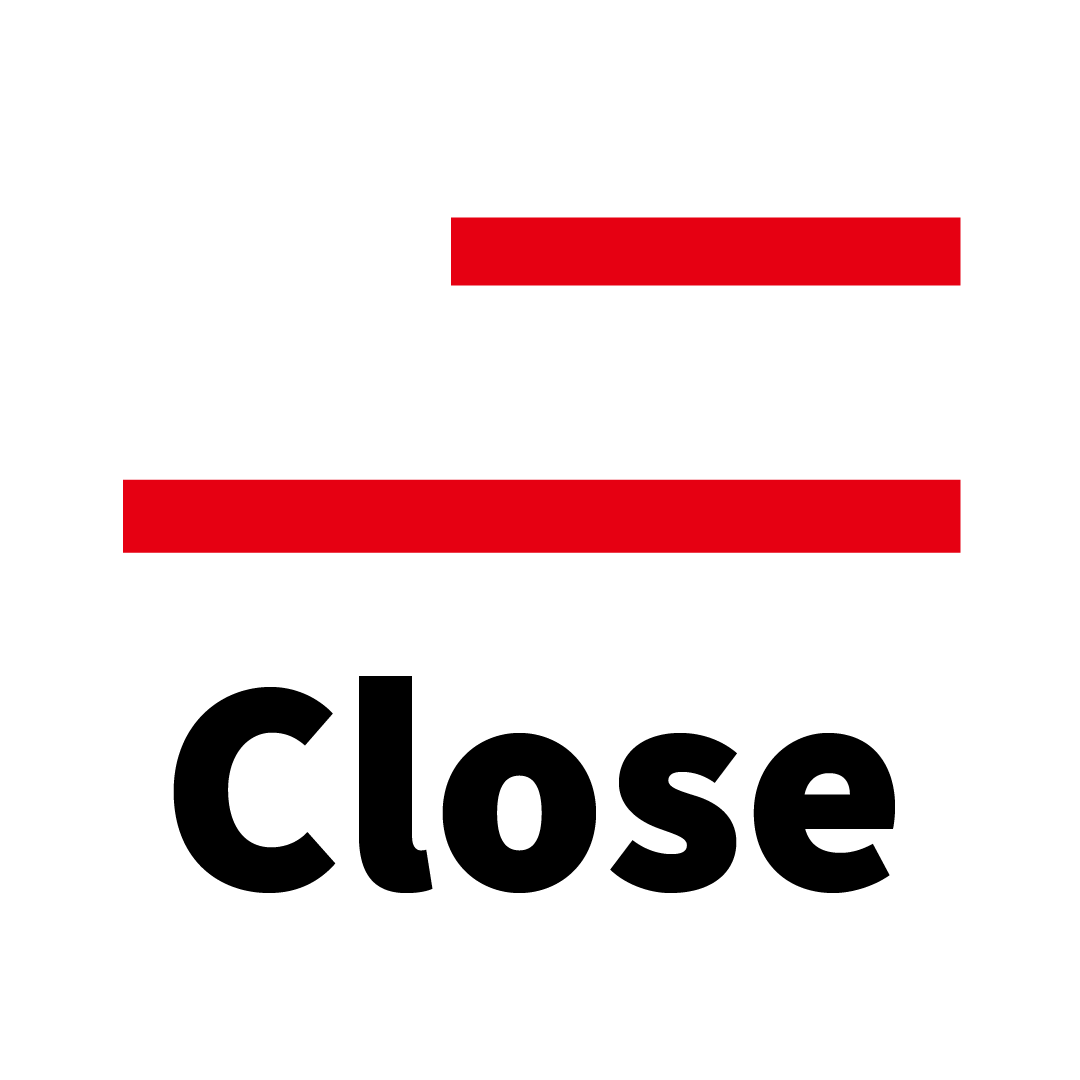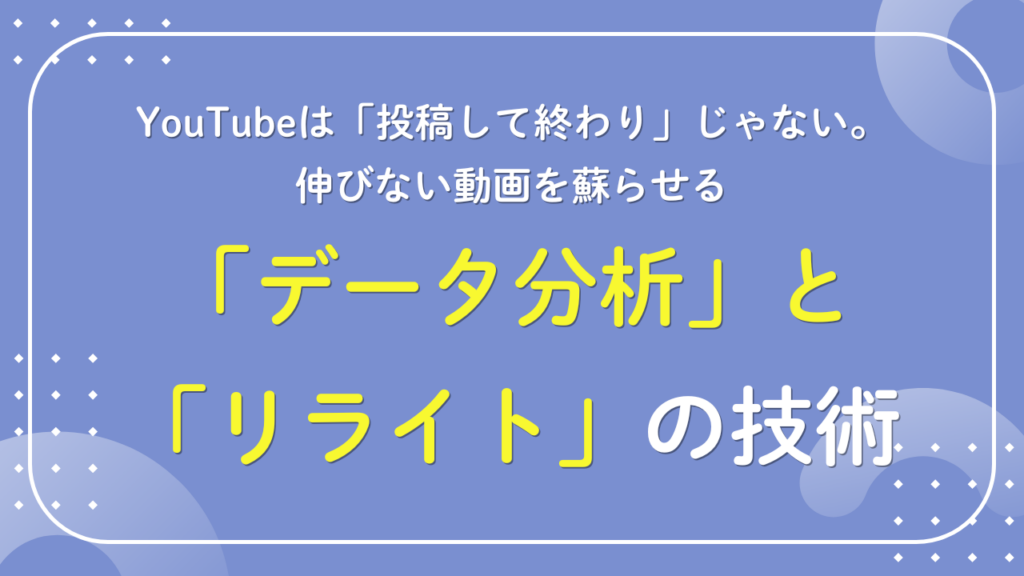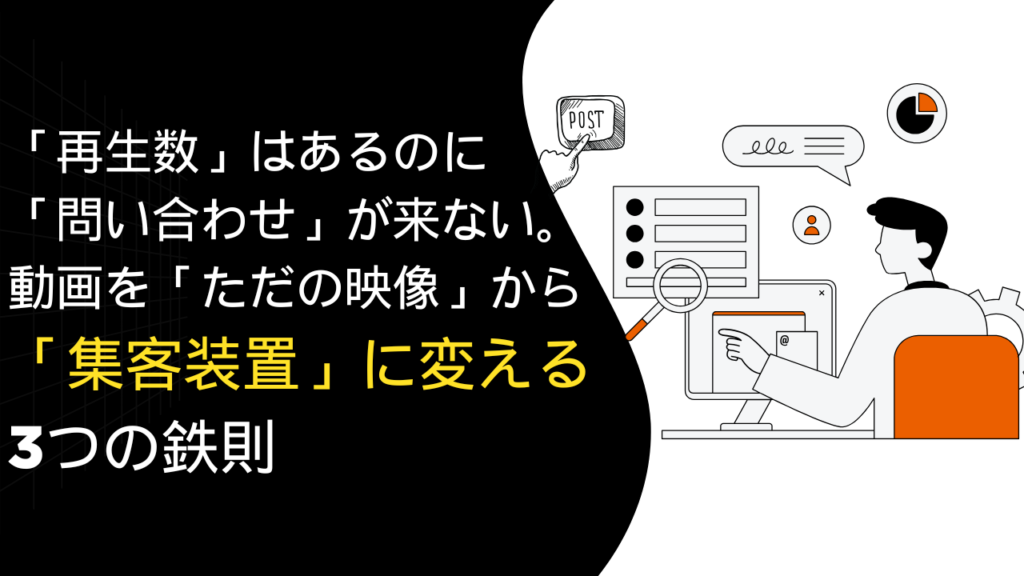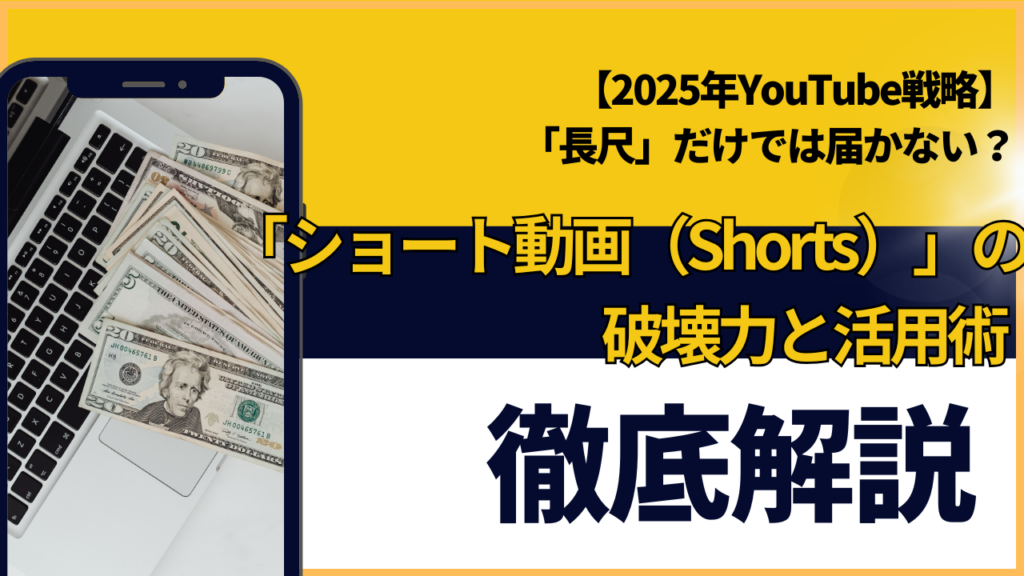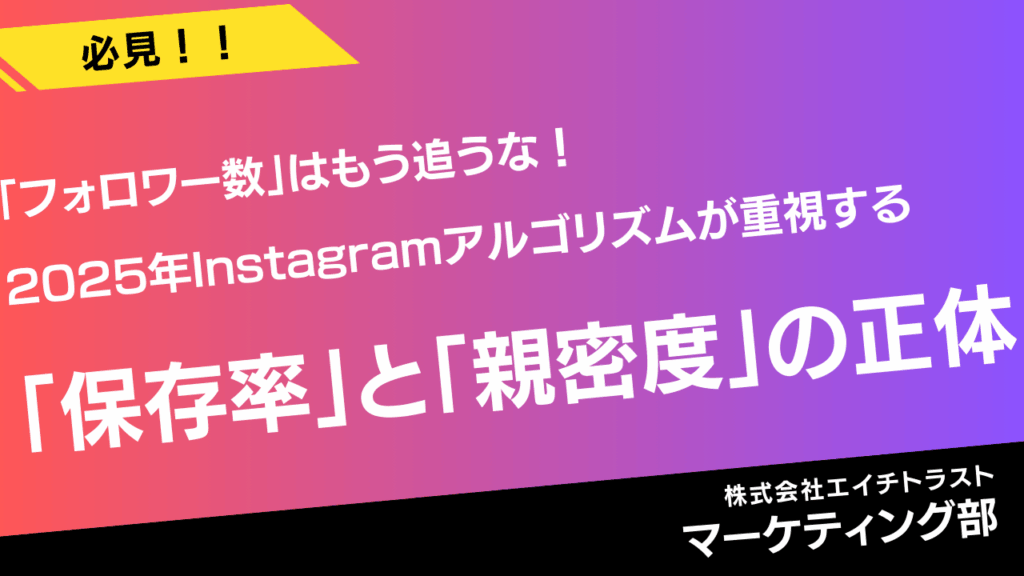生成AIが書いたJavaScriptをレビューするスキルが求められる理由 -エンジニアY-
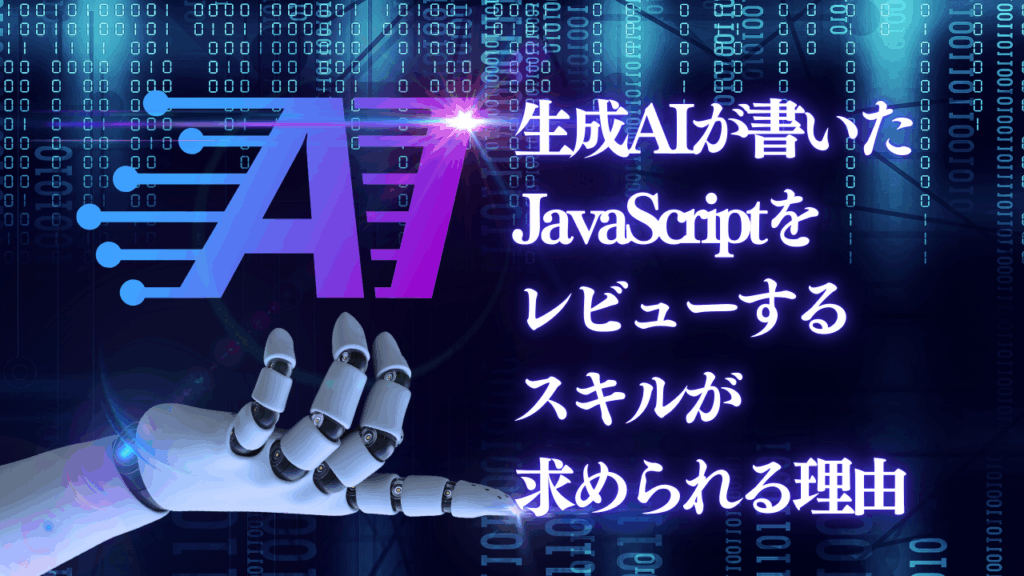
こんにちは、エンジニアのYです。
最近、ChatGPTやGitHub Copilotを使ってJavaScriptを書いてみた人、多いんじゃないでしょうか。実際にやってみるとわかるんですが、かなり完成度の高いコードを一瞬で吐き出してくれるんですよね。たとえば「Reactでモーダルを作って」とお願いすると、それっぽいコードがすぐに手に入る。正直、「これでもうコード書かなくていいのでは?」と思うくらい便利です。
でも、ここで出てくるのがレビューする力です。AIが出してくれたコードをそのまま本番に突っ込むのは、かなりリスキー。だからこそ、開発者には「AIが生成したコードを見極める目」がこれまで以上に求められていると感じます
なぜそのまま使えないのか?
理由はいくつかあります。まずセキュリティリスク。AIは文脈を完全に理解しているわけではないので、XSS対策や入力バリデーションが抜け落ちているケースがよくあります。また、非同期処理の扱い方が曖昧だったり、メモリリークを起こしそうな書き方になっていることも。
もう一つは可読性と保守性。AIが出すコードは、ときどき「正しく動くけど、なぜこう書いたのかよくわからない」ものがあります。パッと見は動いているのでスルーしたくなるんですが、チーム開発の現場では長期的に見て技術的負債になりかねません。
レビューで見るべきポイント
じゃあ具体的にどうレビューすればいいか。僕が気をつけているのは大きく三つです。
まず意図の確認。AIが出したコードは、要件を本当に満たしているか?表面的には動いても、ビジネスロジックがズレていないかを確認します。
次にベストプラクティスとの照合。ReactならHooksの使い方、Next.jsならSSRとCSRの扱いなど、フレームワークの推奨に沿っているかどうかを見ます。
最後に長期的な運用を意識した設計。例えば無駄にネストが深くないか、変数名は意味が通じるか、不要な依存は増えていないか。これらはAIが苦手な部分なので、人間の判断が欠かせません。
“書く力”から“読み解く力”へ
面白いのは、これまでエンジニアに求められてきた「コードを早く書く力」よりも、「生成されたコードを正しく理解し、取捨選択する力」のほうが重要になってきている点です。言い換えれば、“書く”から“読み解く”へのシフト。
もちろん、AIはどんどん賢くなっていくでしょう。でも、どれだけ進化しても、プロダクトの目的やユーザー体験、システム全体の設計を理解して判断できるのは人間です。AIが書いたJavaScriptをそのまま信用するのではなく、「これは本当にウチのプロダクトに合っているのか?」と突き詰められる人が、これからの現場では強いと思います。
まとめ
生成AIは間違いなく開発効率を上げてくれます。でも、AIが書いたコードをレビューせずに使うのは危険。だからこそ、これからのWebエンジニアには「コードを早く書く」より「コードを正しく読み解き、レビューできる」スキルが求められます。
AIが優秀な“相棒”になりつつある今、僕たちの仕事はますます「人間にしかできない判断」に集中していくのかもしれません。
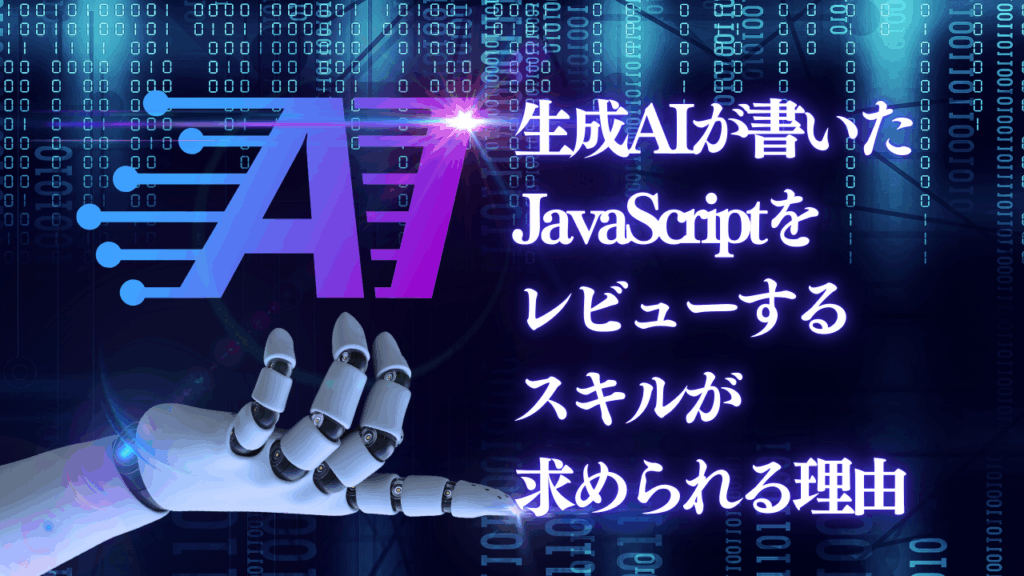
こんにちは、エンジニアのYです。
最近、ChatGPTやGitHub Copilotを使ってJavaScriptを書いてみた人、多いんじゃないでしょうか。実際にやってみるとわかるんですが、かなり完成度の高いコードを一瞬で吐き出してくれるんですよね。たとえば「Reactでモーダルを作って」とお願いすると、それっぽいコードがすぐに手に入る。正直、「これでもうコード書かなくていいのでは?」と思うくらい便利です。
でも、ここで出てくるのがレビューする力です。AIが出してくれたコードをそのまま本番に突っ込むのは、かなりリスキー。だからこそ、開発者には「AIが生成したコードを見極める目」がこれまで以上に求められていると感じます
なぜそのまま使えないのか?
理由はいくつかあります。まずセキュリティリスク。AIは文脈を完全に理解しているわけではないので、XSS対策や入力バリデーションが抜け落ちているケースがよくあります。また、非同期処理の扱い方が曖昧だったり、メモリリークを起こしそうな書き方になっていることも。
もう一つは可読性と保守性。AIが出すコードは、ときどき「正しく動くけど、なぜこう書いたのかよくわからない」ものがあります。パッと見は動いているのでスルーしたくなるんですが、チーム開発の現場では長期的に見て技術的負債になりかねません。
レビューで見るべきポイント
じゃあ具体的にどうレビューすればいいか。僕が気をつけているのは大きく三つです。
まず意図の確認。AIが出したコードは、要件を本当に満たしているか?表面的には動いても、ビジネスロジックがズレていないかを確認します。
次にベストプラクティスとの照合。ReactならHooksの使い方、Next.jsならSSRとCSRの扱いなど、フレームワークの推奨に沿っているかどうかを見ます。
最後に長期的な運用を意識した設計。例えば無駄にネストが深くないか、変数名は意味が通じるか、不要な依存は増えていないか。これらはAIが苦手な部分なので、人間の判断が欠かせません。
“書く力”から“読み解く力”へ
面白いのは、これまでエンジニアに求められてきた「コードを早く書く力」よりも、「生成されたコードを正しく理解し、取捨選択する力」のほうが重要になってきている点です。言い換えれば、“書く”から“読み解く”へのシフト。
もちろん、AIはどんどん賢くなっていくでしょう。でも、どれだけ進化しても、プロダクトの目的やユーザー体験、システム全体の設計を理解して判断できるのは人間です。AIが書いたJavaScriptをそのまま信用するのではなく、「これは本当にウチのプロダクトに合っているのか?」と突き詰められる人が、これからの現場では強いと思います。
まとめ
生成AIは間違いなく開発効率を上げてくれます。でも、AIが書いたコードをレビューせずに使うのは危険。だからこそ、これからのWebエンジニアには「コードを早く書く」より「コードを正しく読み解き、レビューできる」スキルが求められます。
AIが優秀な“相棒”になりつつある今、僕たちの仕事はますます「人間にしかできない判断」に集中していくのかもしれません。