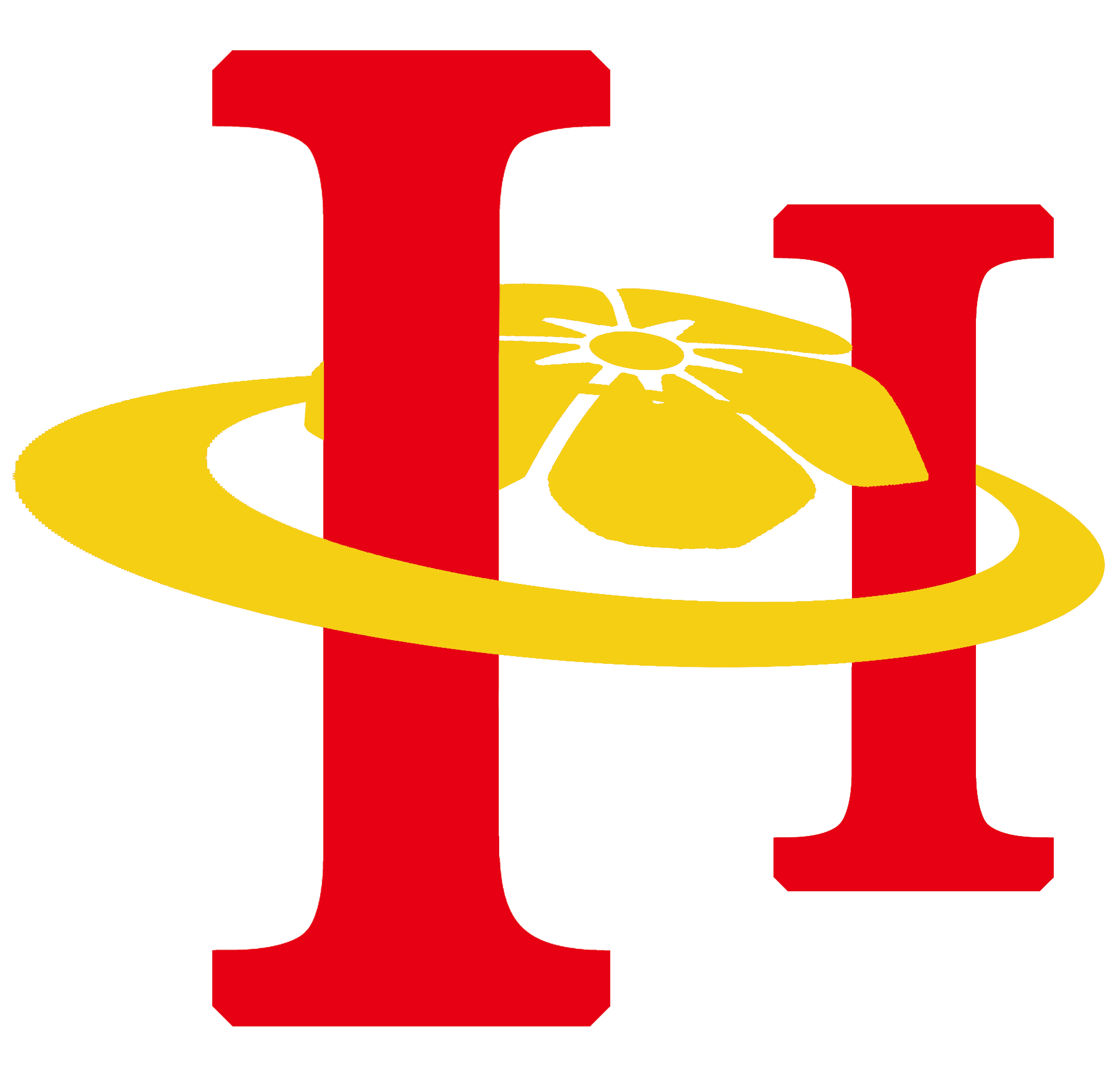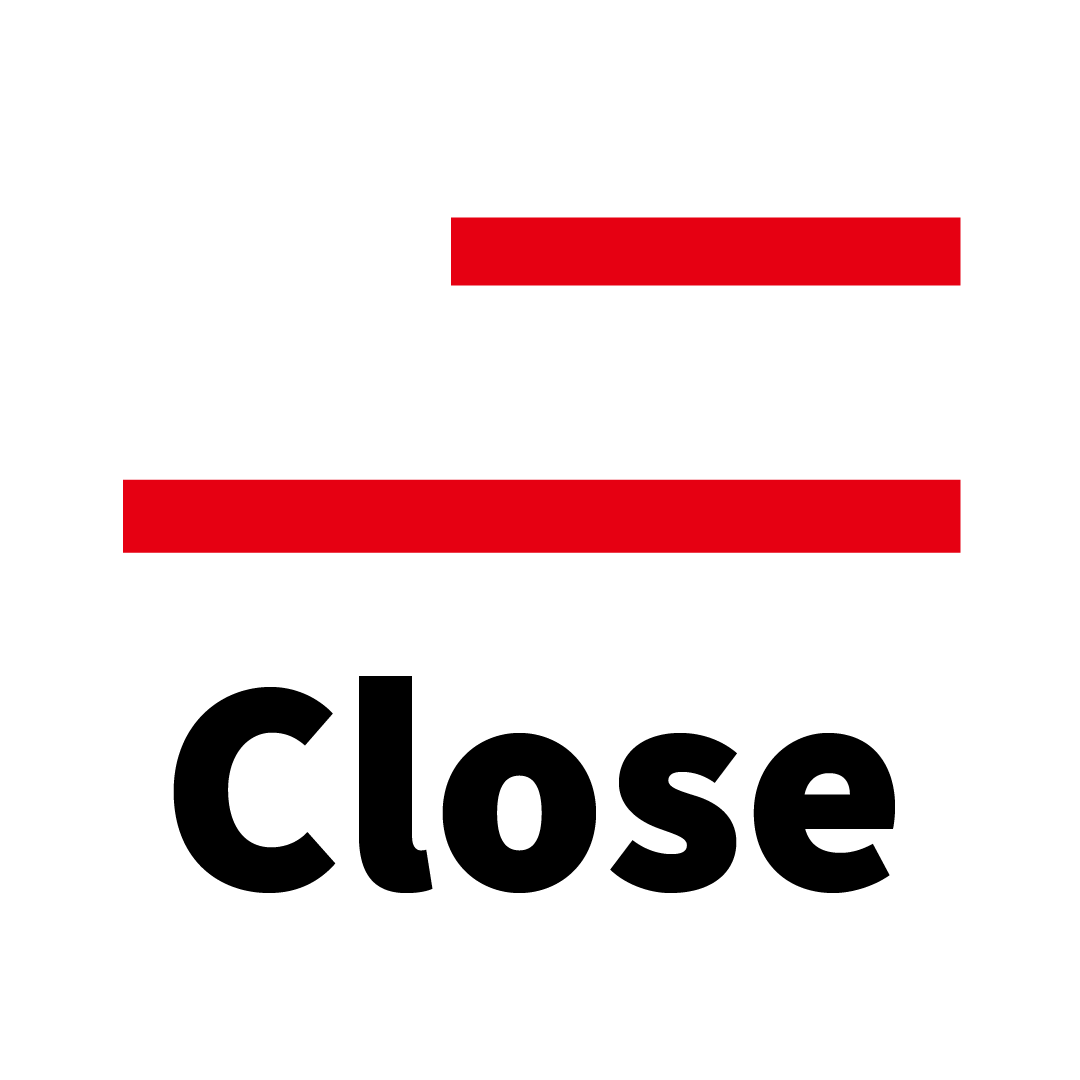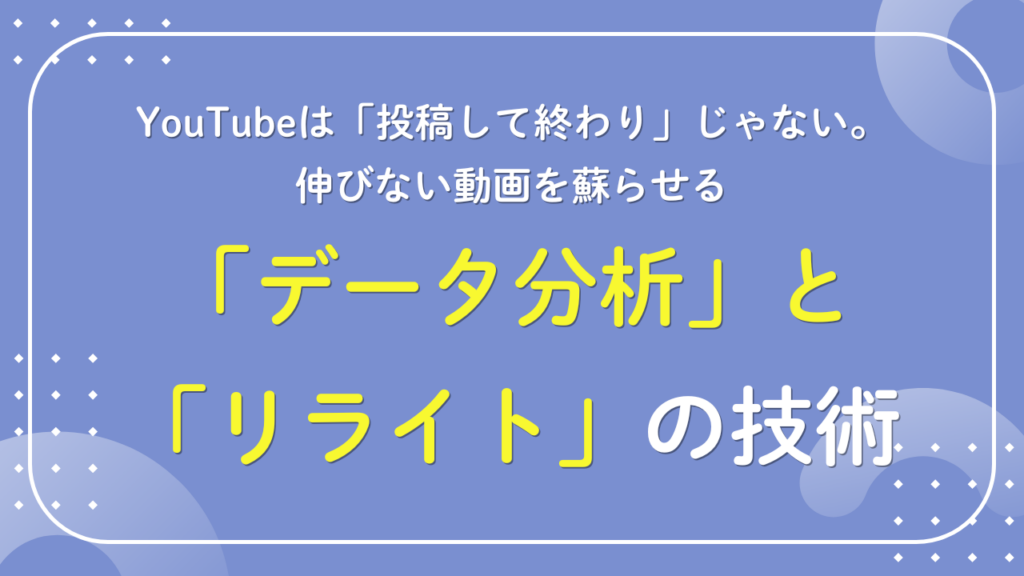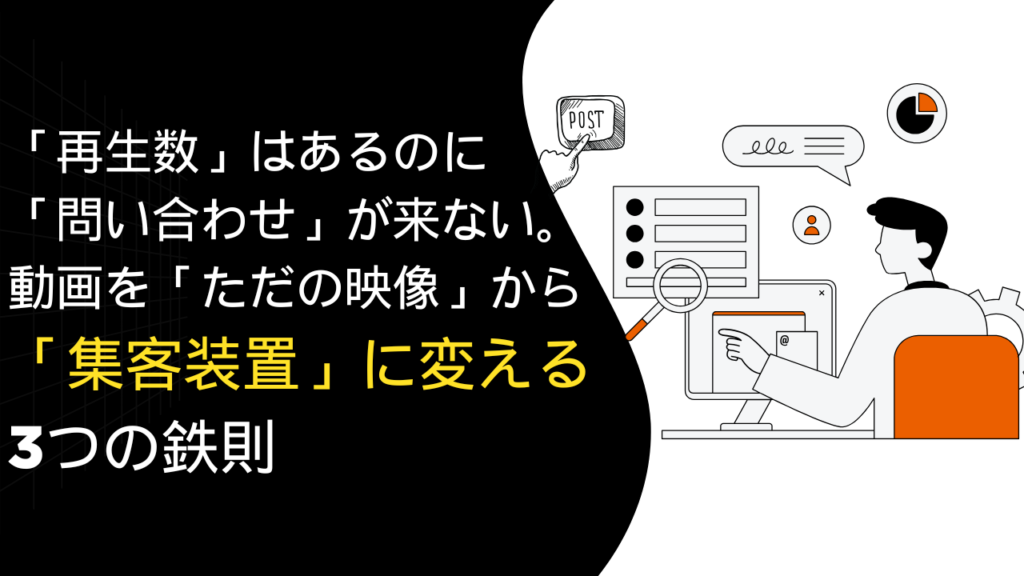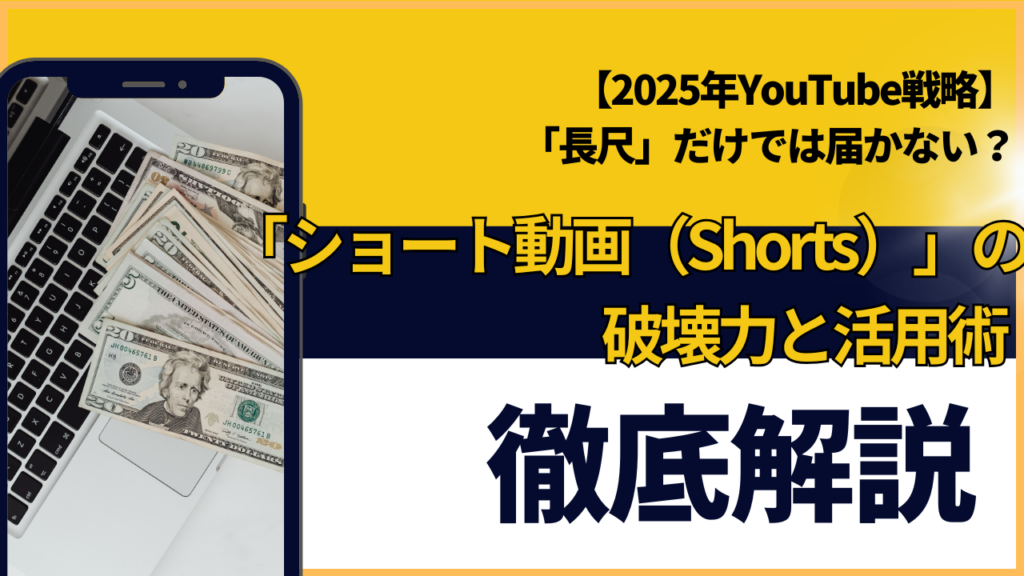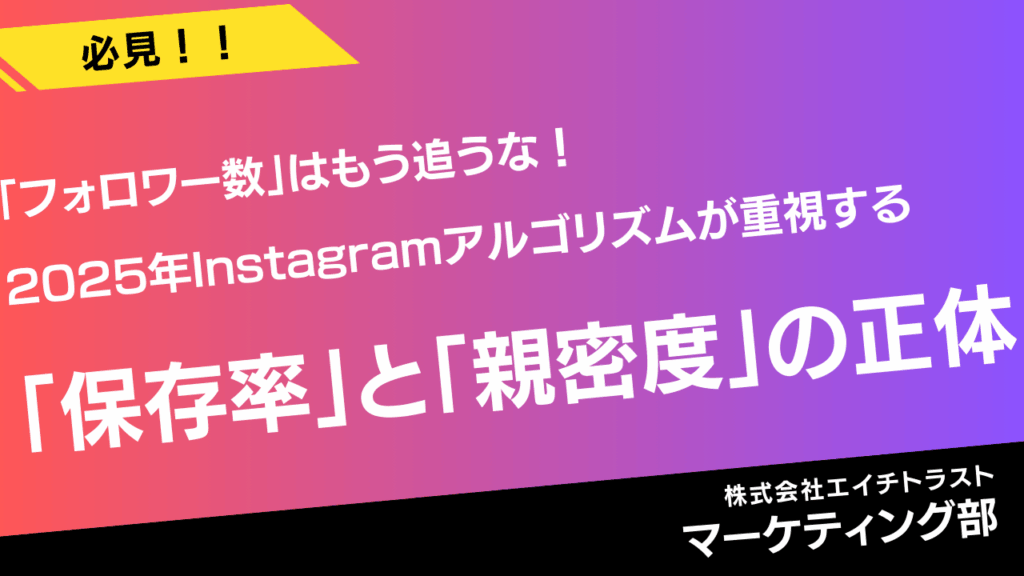AI生成コードはそのまま使える?“補完力”と“設計力”のバランス -エンジニアA-
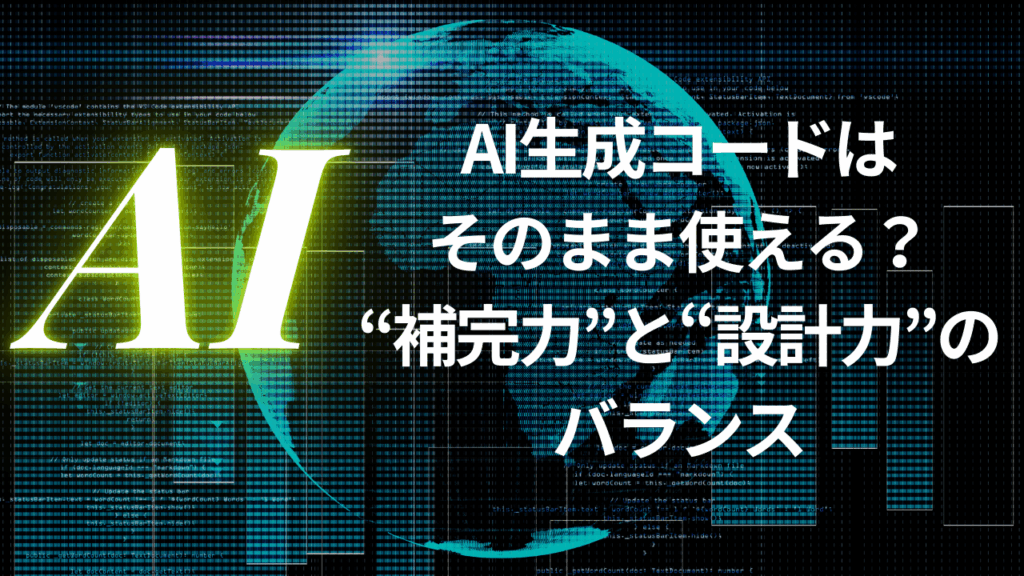
こんにちは、エンジニアのAです。
最近、GitHub CopilotやCursor、ChatGPTといったAIコード補完ツールを使う機会が増えてきました。開発スピードが格段に上がる一方で、「AIが書いたコードをそのまま使っていいのか?」という疑問に直面する場面も少なくありません。今日はそのあたりを整理してみたいと思います。
1. AIコード補完の強み ― “瞬発力”
AIコード補完の一番の強みは瞬発力です。
・繰り返しの処理を書くときにパターンを提案してくれる
・ライブラリの使い方をサンプル込みで出してくれる
・boilerplate(定型コード)を一瞬で生成してくれる
これらは本当にありがたい。従来なら公式ドキュメントを検索して数十分かかっていた作業が、AIのおかげで数秒に短縮できる。これはエンジニアにとって“時短”だけでなく、思考の流れを止めないという点でも大きなメリットです。
2. そのまま使うリスク ― “穴だらけの便利さ”
しかし、AIが出力したコードはそのままプロダクションに使うにはリスクが多いのも事実です。
・セキュリティ面の考慮不足
SQLインジェクション対策やXSS対策が抜けていることがある。
・冗長・非効率な処理
正しく動くが、パフォーマンス面では最適化されていないケースも多い。
・メンテナンス性の低下
命名規則やチームのコーディング規約に沿っていないコードを生成することも多い。
つまり、AIのコードは「動くもの」を素早く出してはくれるけれど、“設計思想”や“長期的な視点”を持ち合わせていないのです。
3. エンジニアに求められる新しいスキル
ここで重要になるのが、AI時代のエンジニアに求められる読み解く力と設計力です。
・AIが出したコードをレビューできる力
「これはセキュリティ的に問題ないか?」「この処理は冗長ではないか?」を判断できる力。
・チーム設計に沿って修正できる力
AIが書いたコードをそのままではなく、自分たちのアーキテクチャや規約に合うよう整える力。
・設計を先に描ける力
「この機能はどう分割すべきか?」「APIとの責務分担はどうすべきか?」といった設計の軸を持っていないと、AIの補完結果を活かせない。
4. 補完力と設計力の“バランス”
私自身も日々AI補完を使っていますが、感じるのは「AIを信用しすぎないこと」です。
AIは優秀な“相棒”ですが、設計の責任はエンジニアにあります。AIが出してくれたコードを鵜呑みにせず、レビューし、改善し、チーム開発に適応させるプロセスが必須です。
つまり、これからの開発現場では:
・コードを書く作業 → AIが効率化
・設計・レビュー・最適化 → エンジニアが責任を持つ
という役割分担が、ますます鮮明になっていくはずです。
5. まとめ
AIコード補完は確かに便利で、もはや無視できない存在になっています。しかし「速く動くコード」と「長く保てるコード」は別物です。AIが与えてくれる“補完力”を最大限活かしつつ、人間が持つ“設計力”でそれを整えること。このバランスを取れるエンジニアこそ、これからの現場で強く求められるのではないでしょうか。
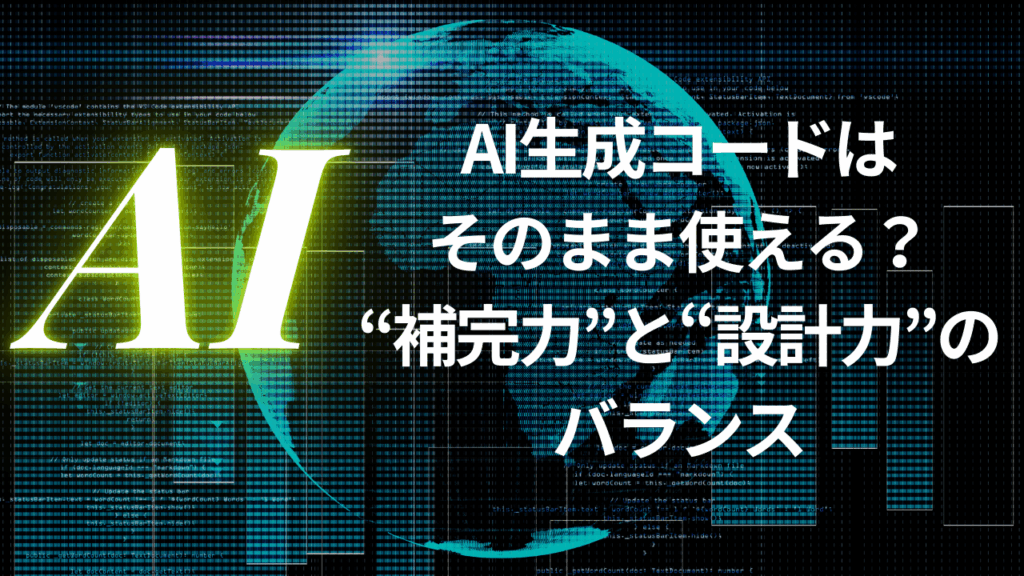
こんにちは、エンジニアのAです。
最近、GitHub CopilotやCursor、ChatGPTといったAIコード補完ツールを使う機会が増えてきました。開発スピードが格段に上がる一方で、「AIが書いたコードをそのまま使っていいのか?」という疑問に直面する場面も少なくありません。今日はそのあたりを整理してみたいと思います。
1. AIコード補完の強み ― “瞬発力”
AIコード補完の一番の強みは瞬発力です。
・繰り返しの処理を書くときにパターンを提案してくれる
・ライブラリの使い方をサンプル込みで出してくれる
・boilerplate(定型コード)を一瞬で生成してくれる
これらは本当にありがたい。従来なら公式ドキュメントを検索して数十分かかっていた作業が、AIのおかげで数秒に短縮できる。これはエンジニアにとって“時短”だけでなく、思考の流れを止めないという点でも大きなメリットです。
2. そのまま使うリスク ― “穴だらけの便利さ”
しかし、AIが出力したコードはそのままプロダクションに使うにはリスクが多いのも事実です。
・セキュリティ面の考慮不足
SQLインジェクション対策やXSS対策が抜けていることがある。
・冗長・非効率な処理
正しく動くが、パフォーマンス面では最適化されていないケースも多い。
・メンテナンス性の低下
命名規則やチームのコーディング規約に沿っていないコードを生成することも多い。
つまり、AIのコードは「動くもの」を素早く出してはくれるけれど、“設計思想”や“長期的な視点”を持ち合わせていないのです。
3. エンジニアに求められる新しいスキル
ここで重要になるのが、AI時代のエンジニアに求められる読み解く力と設計力です。
・AIが出したコードをレビューできる力
「これはセキュリティ的に問題ないか?」「この処理は冗長ではないか?」を判断できる力。
・チーム設計に沿って修正できる力
AIが書いたコードをそのままではなく、自分たちのアーキテクチャや規約に合うよう整える力。
・設計を先に描ける力
「この機能はどう分割すべきか?」「APIとの責務分担はどうすべきか?」といった設計の軸を持っていないと、AIの補完結果を活かせない。
4. 補完力と設計力の“バランス”
私自身も日々AI補完を使っていますが、感じるのは「AIを信用しすぎないこと」です。
AIは優秀な“相棒”ですが、設計の責任はエンジニアにあります。AIが出してくれたコードを鵜呑みにせず、レビューし、改善し、チーム開発に適応させるプロセスが必須です。
つまり、これからの開発現場では:
・コードを書く作業 → AIが効率化
・設計・レビュー・最適化 → エンジニアが責任を持つ
という役割分担が、ますます鮮明になっていくはずです。
5. まとめ
AIコード補完は確かに便利で、もはや無視できない存在になっています。しかし「速く動くコード」と「長く保てるコード」は別物です。AIが与えてくれる“補完力”を最大限活かしつつ、人間が持つ“設計力”でそれを整えること。このバランスを取れるエンジニアこそ、これからの現場で強く求められるのではないでしょうか。